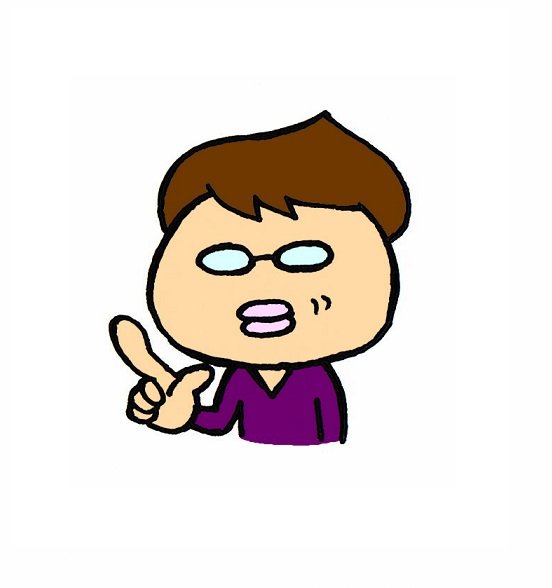
一生脳内から消えることのない言葉とメロディーの融合。40年以上たった今でも鮮やかによみがえる、ピンク・レディーというアイドルの軌跡。幼少期に耳にした歌謡曲の中でも、奇抜さと新しさは群を抜いていた。名画の名ゼリフを模したり、SFやオカルトにたとえて、男女の恋愛感情を軽妙に描いた歌詞。語彙獲得の喜びを味わう時期の子供の心をがっちりと掴んだ。
個人的には、沢田研二が歌う大人の世界、男女の駆け引きと自虐的ダンディズムにもぐっと惹きこまれた(もちろん当時は意味がわかっていないし、ボギーが誰かも知らず)。幼稚園児のとき、私はジュリー派、友達は川崎麻世派で喧嘩したことがあるし、口に含ませた水を噴いて、ジュリーのマネをして怒られたこともある。
日本酒を飲むならぬるめの燗、あぶったイカが肴に最適だと子供の頃に教わったのも八代亜紀から。あげたらキリがないが、すべて阿久悠の作詞と気づいたのは大人になってから。自分の脳内昭和歌謡曲の礎を築いたのはおそらく阿久悠である。
世代がドンピシャなもので、まくらがつい長くなってしまった。
阿久悠の仕事の哲学、栄光だけでなく苦い過去も秘話も含めて、1970年代のアイドル創世記をドラマ化。しかも主役が宇野祥平と知って、いてもたってもいられなかったのが『アイドル誕生 輝け昭和歌謡』だ。
実は、阿久悠が主人公のドラマはこれが初ではない。日テレが2017年の『24時間テレビ』のドラマスペシャルで「時代を作った男 阿久悠物語」を放送した。キャスティングの違和感が拭えず、あくまでチャリティーと称したお祭り内の一幕だった。ま、今となっては「帝国への忖度」「募金の着服」が暴かれて、悪しき象徴になったわけだが。
一方、こちらはNHKが本気を出して、というよりは、脚本・児島秀樹の本気と敬意と執念が結実した名作と言ってもいい(あ、断片的な情報からの想像ね)。作詞は5000曲以上、シングル売上枚数は6834万枚、時代を読み取る才能と卓越したセンスで昭和歌謡界を牽引した天才の人物像を、あますところなく描くことに成功した感がある。正月に再放送もあるので、ポイントをまとめておこう。
完璧なキャスティングに敬意を感じる
なんといっても宇野祥平。阿久悠のプライドとこだわり、不器用さやコンプレックス、天才の孤独と嫉妬と苦悩……すべて見事に体現したのではないだろうか。

宇野は名バイプレイヤーとして数多のドラマや映画に出演。場末のスナックの常連客から人を見下すバカ社長、気の弱い教師やひとこと余計な夫など、この社会の隅々に生きる、ありとあらゆる人間をリアルに演じてきた(朝ドラ『ブギウギ』ではゴンベエさんね)。
映画『罪の声』では、幼少時より犯罪組織に人生を奪われ、罪の意識に苛まれてきた男性を演じ、数々の映画賞で助演男優賞を総なめにした。彼が演じる数十秒には「その人の数十年」が映し出されるという、稀有な俳優である。今回は、よく観ると細部はそんなに似ていないのに、雰囲気が阿久悠そのもの。
そして、劇中で阿久のライバルとして描かれている敏腕プロデューサー・酒井政利を、ホントにそっくりで色気のある三浦誠己が演じた。もうこれだけで「作品は成功した」と言ってもいい。

時のアイドルたちも、雰囲気やたたずまいそのものが近い女優陣を配置。山口百恵を吉柳咲良、桜田淳子を山口まゆ、ピンク・レディーを山谷花純と中川紅葉が演じて、私は違和感なく魅了された。ちなみに若かりし頃の欽ちゃんを演じたたむたむもかなり再現度が高かった。

他にも、昭和のギラギラした芸能界の裏側を再現するのにふさわしい名優揃い。阿久の盟友である若手作曲家・都倉俊一を宮沢氷魚、日テレプロデューサーの岡田薫を萩原聖人、元ミュージシャンでレコード会社社員の飯田久彦を田村健太郎、名振付師の土居甫を迫田孝也が演じ、忖度や事務所の政治力を排したキャスティングに制作陣の本気度を感じた。
嫉妬も後悔も矮小さも描き切る
実在の人物をドラマで描くとき、テレビ局はなにかと色を付けたり、清く盛ったりする。もちろん実話に基づくフィクションなので、なんらかの演出はあるだろう。それでも阿久悠をただただ天才と崇め奉る物語ではなかったところがいい。
「プライドが高くて、負けず嫌いで、かっこつけで、不器用で、モテないコンプレックスも持っているのに、それをおくびにも出さない、やせがまんの男」として丸裸に剝いた。生身を描いたからこそ、制作陣の敬意の深さと温度が伝わってきた。
例えば、阿久が花の中三トリオ(桜田淳子・山口百恵・森昌子)の楽屋に無理やり連れていかれたシーン。今をときめくアイドルたちが待ち時間にスタッフとともにハンカチ落としを始める。しかし、気を遣ってか、誰ひとりとして阿久にはハンカチを落とさず、いじけた阿久がぶんむくれて楽屋を出ていく。いい年した大人のこういう矮小さは、逆に人物に奥行をもたせるから大好物である。
阿久自身が企画し、審査員もつとめた名物オーディション番組『スター誕生』で、「歌はあきらめたほうがいいかもしれないね」とこきおろしたのが山口百恵。その後、酒井が百恵をプロデュースし、センセーショナルな曲で大ヒットさせる。

しかも阿久の盟友である都倉に作曲を依頼。スターの資質を見抜く酒井との熾烈なヒット曲争い、自分をこきおろした阿久に作詞を依頼しない百恵との確執。阿久は後悔や嫉妬をエネルギーに、キャンディーズや百恵に対抗できるアイドルと革新的な歌謡曲を目指す。そして生まれたのがピンク・レディーというわけだ。
芸能界で革新を目指す人の矜持
宇野と三浦のセリフには、時代の先駆者としての矜持や覚悟、豊かな感性がぎっしり詰まっていた。阿久と酒井のアイドルの概念の違いも興味深かった。阿久は「ぽっと出に使う言葉ではない。時代のアイコンにふさわしい言葉だ」と言い、酒井は「僕の考えるアイドルはつかみどころのなさが必要なの、小賢しさは無用なの。茫洋としたある種の不可解さが大衆を魅了するフェロモンになるわけ」と語る。作詞家とプロデューサー、立場も考え方も違うふたりが芸能界を常に新しく面白くしようと切磋琢磨していたことがわかる。
個人的には阿久の仕事部屋に貼られた付箋に目が釘付けに。
●「女」ではなく「女性」として描く歌を
●時代の中の隠れた飢餓に命中
●一編の小説、一本の映画、一回の演説、一周の遊園地 これと同じボリウムを四分間に盛る
そりゃあ何十年も覚えているわけだよ、阿久悠の作った曲の歌詞を。人の心をつかむ言霊が生み出された背景に、納得がいった次第。
70年代の伝説のアイドルがいかにして生まれたか。ある意味で「ピンク・レディー物語」と「山口百恵物語」の側面もあり、その栄光の裏事情を知ると同時に、思わず口ずさんでしまう昭和の歌謡曲や懐かしい映像も流れる愉しみ。50歳以上の人にぜひ薦めたいところだが、昭和歌謡の自由度やある種のダサさは若者の間でも人気が出てきているそうだ。
アイドルに歌唱力を問わなくなり、親近感とのびしろ優先。大所帯&口パク、ヒットの法則をなぞらえるだけで飽和状態の令和。それも文化のひとつで時代のアイコンではあるけれど、このドラマを観ると「昭和歌謡の世界は常に新しさと面白さとクオリティを求めて、こんなにも熱量過多だったのか」と驚くこと間違いなし。お若い方にもぜひ観てほしい。
ライター・コラムニスト・イラストレーター
1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業。健康誌や女性誌の編集を経て、2001年よりフリーランスライターに。週刊新潮、東京新聞、プレジデントオンライン、kufuraなどで主にテレビコラムを連載・寄稿。NHKの「ドキュメント72時間」の番組紹介イラストコラム「読む72時間」(旧TwitterのX)や、「聴く72時間」(Spotify)を担当。著書に『くさらないイケメン図鑑』、『産まないことは「逃げ」ですか?』『親の介護をしないとダメですか?』、『ふがいないきょうだいに困ってる』など。テレビは1台、ハードディスク2台(全録)、BSも含めて毎クールのドラマを偏執的に視聴している。



