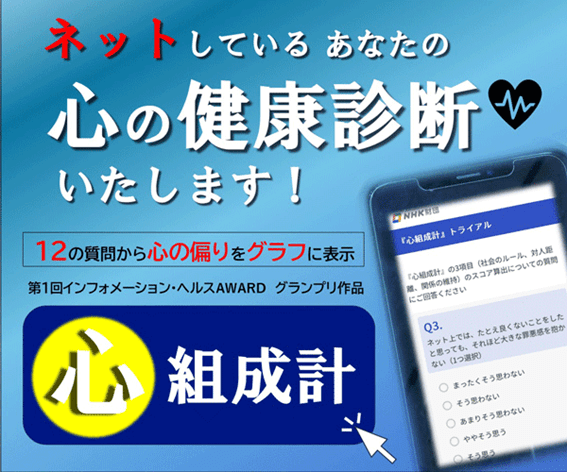大切なことをどのように伝えるか。概念や考え方をいかにイメージで表現するか。そこにテレビの醍醐味があるといえるだろう。
知の巨人が亡くなったあとの大きな空白。その喪失感を、NHKスペシャル「見えた 何が 永遠が~立花隆 最後の旅~」(4月30日放送)は、蔵書で埋め尽くされた部屋の中で笑う生前の立花隆さんの姿と、がらんどうになった同じ空間とのコントラストを通して描いていた。
故人の遺志によって、膨大な書籍は古書店に売られてしまったのだという。いわば、立花さんの生涯そのものとさえ言える本の数々を残さなかったのはどうしてか? なぜ、立花さんは人生の最後に「無」となることを選んだのか? 一気に惹きつけられる、見事な導入部分だった。

長年立花さんと一緒に番組をつくってきたNHKの岡田朋敏さんが、残された資料や、取材のVTRをもとに探っていく。立花さんが岡田さんに発した言葉や、残された文章をもとにいろいろ推測をするなど、取材者としての岡田さんの心の旅路が、立花さんのそれと重なっていく。
生前、『宇宙からの帰還』や、『精神と物質』、『臨死体験』など、数々の本を世に問うた立花隆さん。番組は、その中でも、立花さんご本人が重要な著作の一つだったと考えていたという『エーゲ 永遠回帰の海』に焦点を当てる。
「記録された歴史などというものは記録されなかった現実の総体にくらべたら宇宙の総体と比較した針先ほどに微小なものだろう」
「宇宙の大部分が虚無の中に呑み込まれてあるように歴史の大部分もまた虚無の中に呑み込まれてある」
「見えた何が永遠が」
受け手の魂に迫ってくる立花さんの言葉を、番組は、さまざまな映像を用いて印象的に演出していた。伝わってきたのは、立花さんの生命観のようなものである。

人間は死すべき存在であると認識し、「いのち連続体」という言葉を口にする立花さんが、ジャーナリスト仲間だった筑紫哲也さんを振り返って話しているうちに涙ぐむシーンは感動的だった。
ご自身が病気になったことをきっかけにがんについての探求を始めた立花さんが、「がんの強さは生命の強さ」であり、「がんは半分は自分で半分はエイリアン」であるという境地に達した、そのプロセスが番組としての一つのクライマックスであった。
生前の立花さんと仕事をした文藝春秋元社長の平尾隆弘さんは、インタビューの中で立花さんは常に「境界」を探求していた人だったと振り返る。「生」と「死」、「地球」と「宇宙」、そして「人間」と「サル」。立花さんのお仕事の背後にあった「境界」をめぐる根本的な衝動が腑に落ちてくる。
自分が誰なのか、今どこにいるのか、今がいつなのか? 医学の分野で使われることの多い「見当識」の概念を、人類全体の置かれた状況にあてはめ、私たちという存在の本質をつきつめようとした立花隆さんの探求の旅。
記憶に残る番組とは、一体なんだろう。構成や映像などの技術的なことの積み重ねも大切だが、やはり最後は人々の「思い」ではないか。
一生を人類の「来し方行く末」を理解することにささげた立花隆さんの「思い」と、一緒に番組をつくってきた岡田朋敏さんの「思い」が交錯した49分。そこには、強く長く記憶に残るであろう鮮烈なインパクトがあった。
1962年、東京生まれ。東京大学理学部、法学部卒業後、同大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て、「クオリア」(感覚の持つ質感)をキーワードとして脳と心の関係を研究。文芸評論、美術評論などにも取り組む。NHKでは、〈プロフェッショナル 仕事の流儀〉キャスターほか、多くの番組に出演。