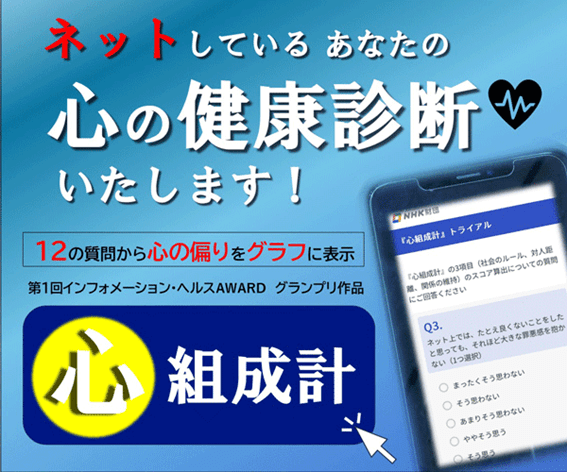私が記憶しているもっとも古い大河ドラマは、1970年、私が8歳になった年に放送されていた「樅ノ木は残った」。山本周五郎の小説を原作に、伊達騒動を描いた。中学生のときには、「風と雲と虹と」(1976年)がクラスの中で流行った。特に、平将門を演じた加藤剛さんが女子たちの間で人気だったのを覚えている。
時代が流れて、2021年の「青天を衝け」は、1963年の大河ドラマ第1作「花の生涯」から数えて、60作目。これだけの長きにわたって、NHKの看板番組、そして日本のテレビを代表する存在であり続けているのはすごいことだと思う。
「不易流行」という言葉がある。変わらない存在であり続けるためには、新しいものを取り入れていかなくてはならない。
「青天を衝け」では、渋沢栄一を演じる吉沢亮さん、渋沢千代を演じる橋本愛さん、徳川慶喜を演じる草彅剛さんなどの役者の存在感はもちろんのこと、大河ドラマの王道の中からさまざまな斬新な要素がかいま見える。
演出に、より一層の芸術性を感じるのだ。オープニング映像に取り入れられているダンスや、物語の途中にも時々挟まれる群舞などが、「定番」の印象を鮮やかに更新する。
カメラの感度の向上や高精細の映像といった撮影機材、編集プロセスの進化もあり、圧倒的に映像がきれいになっている。結果として、一つひとつの画面の印象が際立っている。
あるシーンをごく短い時間使うだけでも、観ている人の脳に強烈な記憶となって残るので、「カット」の切り替えがより迅速になったり、その一方で、じっくり見せるところは長いショットが使われたり、映像のリズムにより一層のメリハリがあるのだ。
画面の中で、フォーカスが当たっているところはもちろん、当たっていないところも含めて美しい印象派の絵のよう。セット、野外を通して、書き割りのお芝居というよりは、リアルな世界の空気感が生まれている。
隅々まで神経が行き届いた画作りは、2020年にNHKがドラマとしてまず制作し、黒沢清監督で劇場版映画として公開され、第77回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(最優秀監督賞)に輝いた「スパイの妻」を思い起こさせる。映像技術の進化が、ドラマの文法、演出法を革新しているのだろう。
このような大河ドラマの「新潮流」は、9月12日に放送された第26回「篤太夫、再会する」においても感じられた。
宝台院で渋沢栄一(篤太夫)が徳川慶喜に再会するシーンは見事であった。表情や顔色の微妙な変化を通して、すっかり時代が変わってしまった中で再び対面したかつての「主従」の心情が描かれていたのである。
人間の脳は、相手の顔色から感情を読み取る神経機構を持つ。放送技術の進歩による“大河ドラマの進化”は、視聴者の脳の潜在能力を引き出しつつある。
(NHKウイークリーステラ 2021年10月15日号より)
1962年、東京生まれ。東京大学理学部、法学部卒業後、同大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て、「クオリア」(感覚の持つ質感)をキーワードとして脳と心の関係を研究。文芸評論、美術評論などにも取り組む。NHKでは、〈プロフェッショナル 仕事の流儀〉キャスターほか、多くの番組に出演。