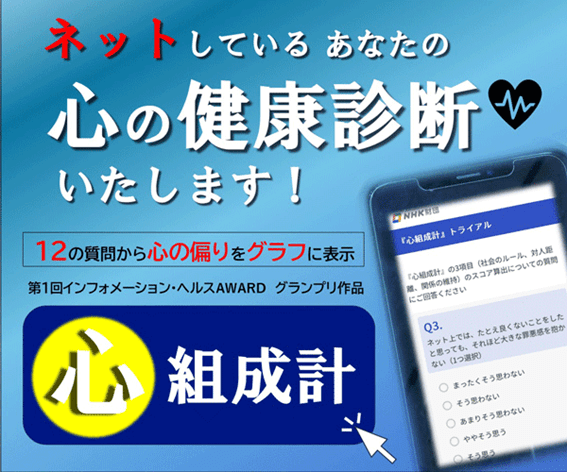〈NHKスペシャル〉「看護師たちの限界線~密着 新型コロナ集中治療室」は、ひとりでも多くの人に見てほしい番組です。去年4月からコロナ患者を受け入れるようになった東京女子医科大学病院(東京都新宿区)の、重症者対応をする集中治療室(ICU)に長期取材した力作でした。
ニュースで危機的だと聞く医療現場。そこで働くひとりひとりの心境の吐露を身近に感じ、日常の表情にほだされますが、しかしその向こうでは新型コロナウイルスの脅威がまだ収まりません。
ICU内の患者のそばでケアをする看護師らの防護服、医療用の手袋。足先まで覆ってガムテープで密閉し、キャップをかぶり、1㌔近くの呼吸器付き防護フェイスシールドで「装備した」と言うしかない姿は重々しく、見ていて言葉を失いました。シールドを外すと残るその輪郭が、過酷な職場を物語ります。
オムツをつけて勤務する人もいるというし、ICU勤務のスタッフ以外も誰もがウイルス対策の保護メガネを着用。ときどき、朗らかなやりとりもあって、やっと画面のこちら側で胸をなで下ろしますが、「この一年よりひどいことはない」と言われるシーンを見る今も、まだまだひどい状況ではないでしょうか。
感染予防で東京都が用意したビジネスホテルの、ベッド、デスクと椅子、壁掛け液晶テレビだけの狭く簡素な部屋で寝泊まりし、晩ごはんはコンビニでサラダとおでん。母親がお弁当を作って持ってきてくれることもあるけれど、ほとんど家族や友人とも会えない。
そんなホテルと病院を往復する25歳の看護師・京河祐衣さんはコロナ病床勤務に日常を捧げ、その疲れは途方もない。笑顔で職場を和ませている看護師9年目の阪井惠さんが、理想のケアが通じず患者の病状の悪化や死に直面する心理も想像を絶します。
「看護職員の疲労はピークを迎えている」と日本看護協会の福井トシ子会長が述べるように、看護師の新型コロナを理由とした離職は、全国の2割以上の病院で起きているのだそう。医療現場では医師が注目されやすいですが、看護師も厳しい職場を支えていて、画面からその多くが女性だと気づきます。女子医大病院の看護師長も、定年退職したが戻ってきた元看護師長も女性。出産を控えている人もいます。
政府統計による、厚労省の「衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」のジェンダーバランスを見ると、2018年の看護師のうち男性はたったの7.8㌫。看護師には、医療現場という過酷な環境で課せられるさまざまな制約のうえに、さらに女性に期待される「控えめに」というジェンダー役割規範の抑圧が重なっているのではないか、と想像してしまいます。
東京オリンピックで何万人もの海外からの訪問者が見込まれている今夏を前に、緊急事態宣言解除の見通しも伝わってきません。そんな政治コミュニケーション不足を感じる中、「医療崩壊が始まっている」「東京の医療を守る」という為政者たちの大きな声が、わたしには遠く聞こえます。それよりもはっきりと手応えの感じられる、番組内のひとりひとりの医療従事者、ケアを受ける患者たち、その家族や友人たち、そんな市井の小さな声にこそ耳が傾けられてほしいです。
(NHKウイークリーステラ 2021年6月25号より)
1982年、高知県生まれ。ライター。ジェンダー、セクシュアリティ、フェミニズムの視点から小説、映画、TVドラマの評、論考を執筆。『キネマ旬報』『新潮』『現代思想』『ユリイカ』などに寄稿。近著に『「テレビは見ない」というけれど』(共著/青弓社)。