
NHK財団は、2017年、旧NHKインターナショナルのころからウクライナ公共放送の支援に取り組んでいます。今回、戦時下となってから初めてキーウを訪れました。目的はウクライナ公共放送の組織体制の強化です。
ウクライナの人々へ正確な情報を伝達する。その使命が果たせる体制の構築に向けた、支援の様子をリポートします。
キーウの「日常」を知ることから
ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナ。首都キーウへの渡航が近づく中、私たちは、日本で安全講習を受けました。
危険地における行動や心構え、空襲警報アプリの使い方、地下シェルターでの過ごし方などが具体的に指示されました。
しかし、ポーランドからの夜行列車で日曜早朝に到着したキーウの駅は、行き交う人々やコーヒーショップで出発を待つ旅行者など、日常の空気が流れていました。
夜間外出禁止令があり、空襲警報はほぼ毎日発令されていましたが、私たちが移動に使う“防弾車”の窓越しに見るキーウの街並みには、渡航前の想像とは異なる“日常”の風景がありました。
歴史ある建造物から、未来の公共放送へ
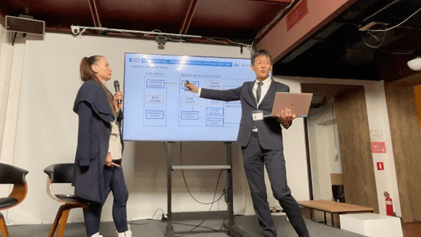
今回、キーウで行った支援の目的はウクライナ公共放送の組織体制強化です。次の3点で、共通認識を作ることを目指しました。
- いかなる時にも情報を届け続ける「バックアップセンター」体制を作る
- NHKの拠点局体制をモデルとした「サポートセンター」体制を整える
- 歴史を伝えるコンテンツを守り、取材情報を有効活用する「アーカイブス」体制を整備する

「サポートセンター」体制構築へ
訪問のハイライトは、2の「サポートセンター」に関するワークショップでした。
ウクライナ全土を6つの地域ブロックに分け、それぞれに拠点を置き、キーウ本部、拠点局、そして地域放送局が連携して業務を行う、というものです。

グループに分かれて活発な議論が行われました。
参加者たちは6つのグループに分かれて意見を交換し議論をまとめていきます。その熱気には目を見張るものがありました。
大きな模造紙に参加者がペンを走らせ、現状の課題や未来へのアイデアを書き出していきます。誰もが主体的に発言し、活発な議論が繰り広げられます。困難な状況下で育まれた一体感と、より良い組織を自分たちの手で創り上げようという強い意志が、会場全体に溢れていました。
各グループの発表では、全参加者の共通認識として「サポートセンター」の必要性が強く示されました。リスクの分散、効率的なリソース運用、地域の実情に合わせた情報発信、そして放送継続のための支援体制……これらについては全てのグループでその重要性が確認されました。
歴史と最新技術の融合
各グループからの提案を表現する手段として、AIによる議論内容の可視化も行われました。

ワークショップで生まれたアイデアやキーワードをAIが解析して、抽象的な“イラスト”を生成しました。
複雑な議論の全体像を全く違う視点で表現することで、参加者たちに新たな発想が生まれたようです。
ウクライナ公共放送のキーウ本部は歴史ある建造物の中にあります。そこで最新技術を用いて未来像を描き出す……その光景は、この放送局が置かれた現状と、あらゆる手段を使って視聴者に公正な情報を発信し続ける意志を表しているように感じました。
困難を越えて情報を届ける
戦時下という極限状況でも、職員たちは公共放送の使命を胸に日々の放送を続け、未来を描いていました。インフラ攻撃や安全確保、フェイクニュースとの戦いなど、課題は多くあります。しかし、彼らの熱意と連帯感は、ウクライナ公共放送がこの難局を乗り越え、ウクライナ社会に不可欠な存在であり続けることを強く感じさせるものでした。
ウクライナ公共放送が、一日も早く平和の下で、その使命を果たせる日が来ることを心から願います。そして、今後もNHK財団は、オンライン会議や日本での研修を通じてウクライナ公共放送への支援を継続していきます。
(取材・文/NHK財団 国際事業本部 齋藤雅浩)

