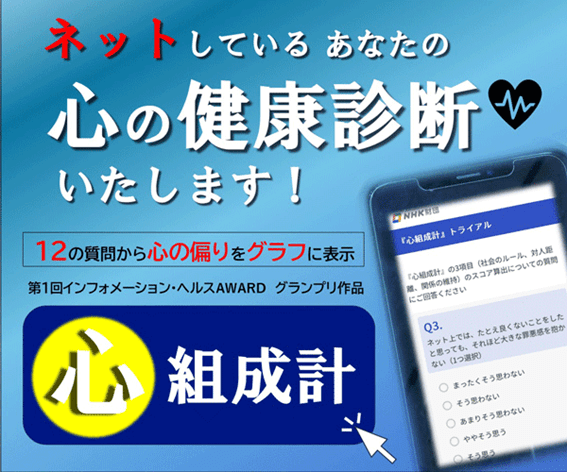武士のもつ“武力”というのは、はっきりいって“暴力”のことだと思います。後世でも、「口でいってわからなければ、腕で教えてやる」などということばが横行しますが、この“腕”というのは“腕力”のことであり、“暴力”のことです。
清盛の時代に武士が“貴族の番犬”として扱われたのは、もちろん身分差別もありますが、同時に武士側にも問題がありました。それはなにかというと、武士がすぐ暴力をふるうという点です。
「問答無用(話しあいなんか必要ない)」
といっては、たちまち腕力で問題を解決します。話しあいをしないということは、「考えない」ということになります。考えないですぐに行動に移るということは、動物とおなじです。
ですから公家などのように
「いつも“考えて”ばかりいてその結果得た結論をどのように表現するか」
と、「思考と表現」にばかりうつつをぬかしている連中からみれば、武士は、“考えない・表現力(ことば)をもたない・犬とおなじ生き物だ”と思われていたのです。
「武」という字のもともとのイミは“ホコ(武器)を止める”ということで、世の中を平和にするというイミでした。「文武両道」という言葉は、
「ホコ(拡大すれば戦争)を止めるためには、チエ(知力)が必要だ」
ということであり、そのチエを養うのが“文(学問や教養)”だとされていたのです。

ですから武士は、
・この世に平和をもたらす責務を負っている
・その責務をさまたげるものに対しては武力を行使する
・しかし武力行使の是非については、チエを発揮しよく考える
・考えるための知力を養うために学問をまなび、教養を身につける
という存在になるのです。
歌をよむことは、この教養の一環であり、そのひとの知性や感性をしるための“メルクマール(目印・指標)”でもありました。そして歌会は、参加者の“知性の競技場”でもあったのです。
(NHKウイークリーステラ 2012年5月4日号より)
1927(昭和2)年、東京生まれ。東京都庁に勤め、広報室長、企画調整局長、政策室長などを歴任。退職後、作家活動に入り、歴史小説家としてあらゆる時代・人物をテーマに作品を発表する。