どうも、朝ドラ見るるです。
裁判官としての仕事に加えて、家庭裁判所の広報活動、家庭相談の手伝い……大忙しのトラコ(寅子)が再会したのは、明律大学の同窓、梅子さんでした!
しかし、まさかの遺産相続バトル勃発中……いや〜、大庭家、ほんとに一筋縄でいかない。亡き夫も、3人の息子も、姑も、愛人まで……。
最終的に、梅子さんは遺産を放棄して、今度こそ家を出る決断を下したわけだけど、そりゃ、そうしたくもなるよね。むしろ、これまで本当によく頑張ったと思う。いずれにしても、梅子さんのこれからの人生が、幸せなものでありますように……!
さて、ここで見るる的、気になりポイント。
大庭家が遺産相続で大揉めしているのはわかったけど、そして、割とよくドラマや映画でも目にするテーマだけど……実際のところ、あんまり相続のルールってわかってないかも。うーん、ここは詳しく教わりたい!
というわけで、今回お話を伺ったのは、「虎に翼」の法律考証をされている、明治大学法学部の村上一博教授です! それじゃ今週もやっていきましょう。教えて、村上先生〜!
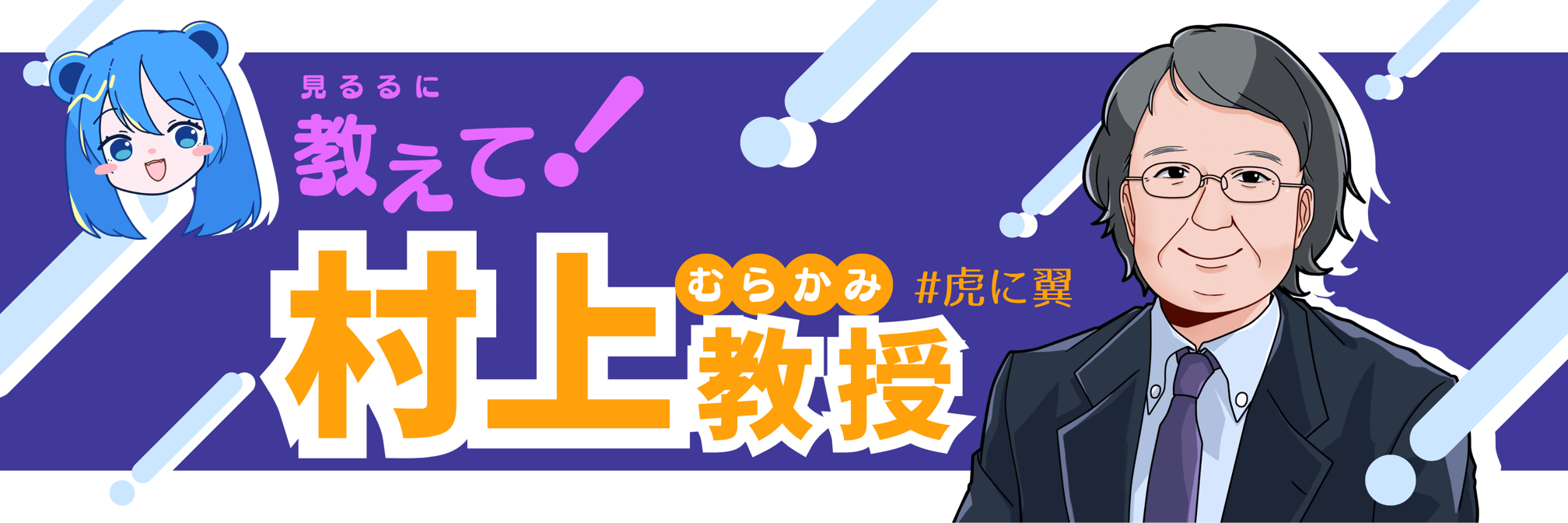
遺産相続バトル〜大庭家の場合〜を徹底解説!
見るる 今週、梅子さんの身に起こった、つまり、大庭家での遺産争いについて、改めて詳しく教えていただきたいのですが……遺産相続のしくみって、一体どうなっているんですか?
村上先生 はい、しっかり復習していきましょう。まず、相続の原則は「遺言」だということは知っていますね?
見るる はい。ドラマでも、梅子さんの夫だった徹男氏が書いたとされる遺言書を、トラコが読み上げていましたよね。「全財産を(愛人の)元山すみれに遺贈する」って。ちょっと、とんでもない遺言だなって思いましたけど……。
村上先生 そうですね(苦笑)。でも、自分が亡くなったあと、その財産をどう処分するかは、自由に決定していいんです。周りは、その内容に、けちのつけようはないわけで。
見るる そうなんですね……。じゃあ、遺言がなかった場合には、どうなるんですか?
村上先生 遺言がなかった場合には、「法定相続」を行うことになります。この時代──1949(昭和24)年当時ですと、父親が亡くなった場合、その財産は、母親(=配偶者)に3分の1、子どもに3分の2が相続され、子どもが複数いる場合は、頭割で均等に分けることになっていました。
見るる ということは、梅子さんが3分の1を相続して、残りを3人の息子が均等に分けるということですよね。でも、遺言書があった場合には……。
村上先生 そう、遺言で書かれていた「愛人に全財産を遺贈」が優先されるわけです。ところが梅子さん、さすが法律を勉強していただけのことはあります。「新しい民法によれば、妻と子は各相続分の2分の1を“遺留分”として請求できるはず」と、三男・光三郎さんに耳打ちしていますよね。
見るる それです、それ! その「遺留分」というのが気になってたんです。これってつまり、どういうことなんですか?
村上先生 先ほどお伝えした通り、相続の原則は遺言です。しかし、この大庭家のように、第三者に全額財産を渡すと遺言で指定されてしまった場合、遺された家族は生活が立ち行かなくなってしまいますよね。これを防ぐためにあるのが「遺留分制度」です。
徹男さんがすみれさんに全財産を渡すという遺言があったとしても、配偶者及び直系の親族──つまり梅子さんと子どもたちは、その2分の1を請求することが可能というわけです。
見るる なるほど! 確かに、全財産が第三者の手に渡ってしまったら、遺族は明日からどうやって生きていけばいいんだ⁉︎ ってなりますもんね。遺言が原則と言いつつ、ちゃんとそのあたりはフォローされているんですね。
村上先生 そういうことです。まあ、結局、あの遺言書は偽造だったわけですが。
見るる 証人の偽装を見破った轟&よねさんはグッジョブでしたよね! そういえば、正式な遺言書には、必ず「証人」が必要なんですか?
村上先生 いえ、普通の遺言であれば証人が必要ありません。でも、今回の徹男さんの場合は、特別方式の「危急時遺言」だったために、証人は3人必要でした。
通常、遺言書は本人が全文を自筆で書き、署名をしてはじめて成立するものです。ただし、遺言者の死期が迫っていて、すぐにでも遺言書を作成しなければいけないという状況においては、代筆が認められています。それが「危急時遺言」。
でも、それに必要な証人が偽装されていたのですから、当然、無効ということになったわけです。
見るる うーん、なるほど! お話をうかがって、ようやく、いろいろわかってきました。
相続法改正の歴史 こうして今に至る──
見るる それで、遺言が無効になったからには、法で定められたとおりの遺産分配になるはずでしたけど……さらに揉めていましたよね。大庭家! 特に、梅子さんに遺産を放棄してほしいと長男・次男が言い出したのには、びっくりしちゃいました。
村上先生 実際、民法改正の直後は、相続による揉めごとが多かったようです。明治民法の意識が残っている男性からすると、「自分の財産を女なんかにやってたまるか」という意識もあったでしょうし、妻がその権利を主張しなかったことで、「相続を放棄した」ことにされてしまったケースもあったでしょうね。
見るる そんなの、本当にありえない! でも、権利を主張するといったって、ちゃんとした知識がないとどうにもならないですもんね。……ん? ちょっと待ってください。ということは、旧民法では、女性の相続権ってどうなっていたんですか?
村上先生 明治民法では、戸主である夫が家の全財産を所有するとされていました。そして、家督相続によって、次の戸主となる長男に、その財産は相続されるものでした。ですから、配偶者である妻に相続権はありませんでした。
見るる え⁉︎ 取り分ゼロってことですか?
村上先生 ええ。家制度のもとでは、そういうことになりますね。しかし戦後の法改正で家督相続制度が廃止され、男女を問わず、亡くなった本人の配偶者に対して、全財産の3分の1の相続が認められたんです。
見るる つくづく改正されてよかった……。でも、現在は、確か配偶者の相続分は「3分の1」ではないですよね?
村上先生 よく気づきましたね。現在、配偶者の相続分は「2分の1」。1980(昭和55)年の改正で引き上げになったんです。
見るる おお〜。ゼロから半分にまであがったと思うと感慨深いです! ところで、この引き上げのきっかけは何だったんですか?
村上先生 当時、「主婦論争」という運動があったんですよ。戦後の主婦の状況をめぐって、「家事労働には経済的にどのくらいの価値があるのか」などの論点で大いに盛り上がった論争でした。
女性たちの主張は、「夫が外でめいっぱい働けるのは、妻が家にいて家庭を守っているから。だから夫が稼いだ財産について、主婦である妻にも半分の権利はあるぞ」というものでした。そして、これをきっかけに、社会に変化が訪れたのです。
見るる へえ〜。今とはだいぶ状況が違うとはいえ、先人の女性たちには頭上がらないです、はい。
村上先生 ほかにも相続法は、少しずつ改正が行われています。たとえば2018(平成30)年に行われた改正では、「長期居住権」という権利が追加されました。
亡くなった夫の財産が家しかなかった場合、妻と子どもで家を2分の1ずつ分けて相続しなくてはなりませんよね。しかし相続にあたって、家そのものをきれいに分割するというわけにはいきませんから、家や土地を売ってお金にして、それを分けるしかありません。
ところが、そうはしたくない、その家に住み続けたいと妻が主張した場合、どうするか。土地建物の評価額を算出して、その2分の1を息子に支払うことができれば解決ですが、それは多くの場合、非現実的ですよね。それに妻が高齢の場合、お金は得られても家をなくすというのは大きな負担になります。
……というわけで、そのような場合、妻は相続時に居住していた家に亡くなるまで住み続けられる、という権利が保障されたわけです。
見るる なるほど、相続法も、時代によってどんどんアップデートされているんですね。
次週!
第14週「女房百日 馬二十日?」7月1日(月)〜7月6日(土)
意味:《どんなものも、はじめのうちは珍しがられるが、すぐに飽きられてしまうというたとえ。妻は百日、馬は二十日もすれば飽きてしまうとの意から。》(辞書オンライン『ことわざ辞典』より)
予告動画が……いつもにましてカオスです。岡田将生さん演じる新キャラ登場、と思いきや、桂場さん、一体どうしてお皿を食べているの? しかも穂高先生が叫んでる⁉︎ その上「あとは君たち若い者に託した」って……意味深な写真って……うわあ、どうなっちゃうのか気になるよ〜!
というわけで、今週の「トラつば」復習はここまで。
来週の先生方の講義も、お楽しみに〜!!
明治大学法学部教授、明治大学史資料センター所長、明治大学図書館長。1956年京都府生まれ。日本近代法史、日本法制史、ジェンダーを専攻分野とする。著書に、『明治離婚裁判史論』『日本近代家族法史論』(ともに法律文化社)など多数。「虎に翼」では法律考証担当として制作に参加している。
取材・文/朝ドラ見るる イラスト/青井亜衣
“朝ドラ”を見るのが日課の覆面ライター、朝ドラ見る子の妹にして、ただいまライター修行中! 20代、いわゆるZ世代。若干(かなり!)オタク気質なところあり。
両親(60&70代・シニア夫婦)と姉(30代・本職ライター)と一緒に、朝ドラを見た感想を話し合うのが好き。




