左前になって店を畳む鱗形屋(演:片岡愛之助)と蔦重(演:横浜流星)が和解したことで、すっかり悪者になっていた“鱗の旦那”の意外な人間味が視聴者に伝えられたドラマ第19回。みなさんはどうご覧になったでしょうか。江戸文芸関係者としては、17世紀から江戸の出版文化を支えた鱗形屋の好感度が多少なりとも上がって、ほっと胸をなで下ろしたところです。

それでも私から見れば、まだまだ“可哀想すぎる”のが、恋川春町(演:岡山天音)です。
ドラマでは律儀に鱗形屋の肩をもって蔦重を毛嫌いするという、なんともイヤな感じを漂わせる人物として描かれていました。そのうえ、青本のイメージを一新し、文学史上、「黄表紙」と呼ばれるジャンルをうちたてた春町の著作『金々先生栄花夢』(安永4年[1775]刊/コラム#8参照)さえ、鱗形屋を介してそのアイデアを提供した蔦重の“手柄”にされるとは!
しかもその後も、ひたすら古くさい作風だとか、本人が堅物なだけに斬新な作品は期待できそうにないとか……。
ドラマで鱗形屋を悪役にした以上、そちらと親しい春町の描き方は残念なものにせざるを得なかったのかも知れません。しかし、ドラマ内で喜多川歌麿(演:染谷将太)に「味がある」と評された独特のゆるい絵や文字もあいまって、実際には、そのおちゃめな作風から黄表紙好きたちが愛して止まない人物なのです。
ドラマのセリフにも出てくる『辞闘戦新根』は、草双紙定番の洒落ことばが化物となって、版元、画工、版木屋たち一同はわれらを崇めるべきだと大暴れするという、出版業界の内輪ネタにして奇天烈な発想と、なんともいえない素朴にして躍動感溢れる絵柄が、ファンとしてはたまらない作品でした。

「鯛の味噌ずで四方のあか」が鯛・酒樽・吸い物椀となって彫工たちを襲う場面。
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892435
そもそも、春町は素人ながら歌麿同様に鳥山石燕(演:片岡鶴太郎)に絵を学び(コラム#18参照)、人気浮世絵師勝川春章(演:前野朋哉)に私淑して浮世絵風の挿絵を描いた人物で、堅物のはずがありません。
また『金々先生栄花夢』に先だって刊行された、“今どきのファッション図鑑”といえる『当世風俗通』と『当世女風俗通』(安永4年、長谷川新兵衛刊)。この2冊の作者(筆名「金錦佐恵流」)には、春町説と朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)説があるものの、独特の脱力感のある絵と版下(文字)はまごうことなき春町のものです。これが描けた春町が“古くさい”わけがないのです。
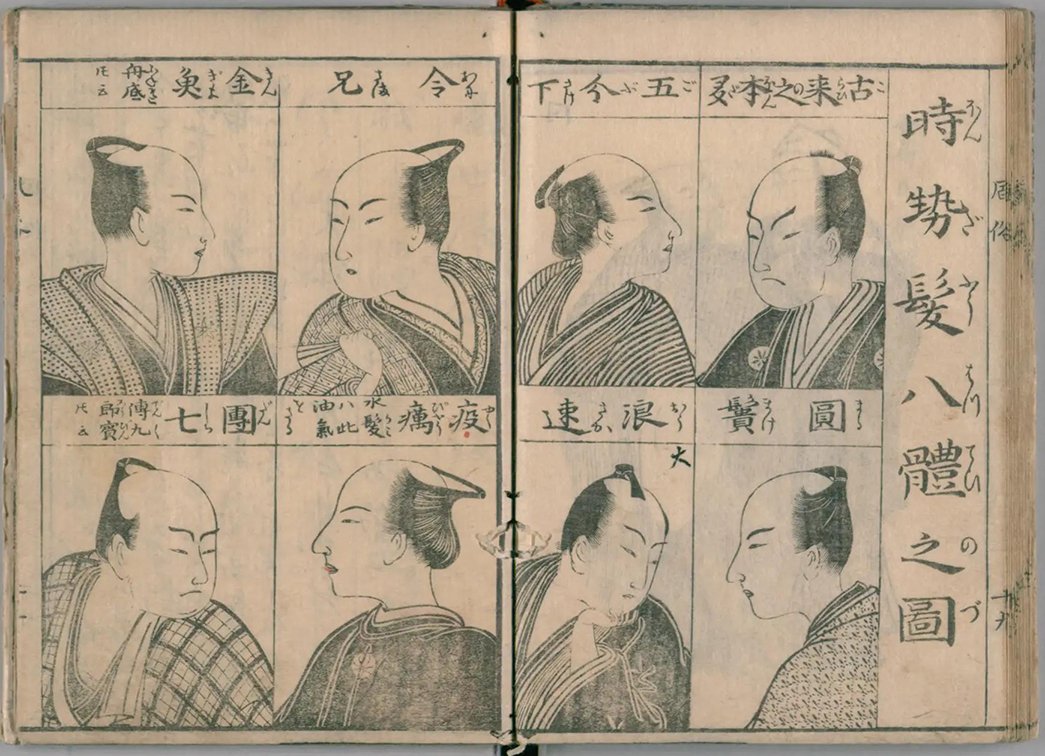
金錦佐恵流 作ほか『当世風俗通』 安永2年 長谷川新兵衛刊
はやりの髪型をカタログ化している。
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2534201
作品から読み解く、春町の通人哲学
もうひとつ、春町の通人(人情・遊興などに通じた粋な人)ぶりが如実に表れているのが『無頼通説法』――春町坊杜撰大和尚による説教を記したという体裁の洒落本です。この中に春町の人となりを探ってみましょう。
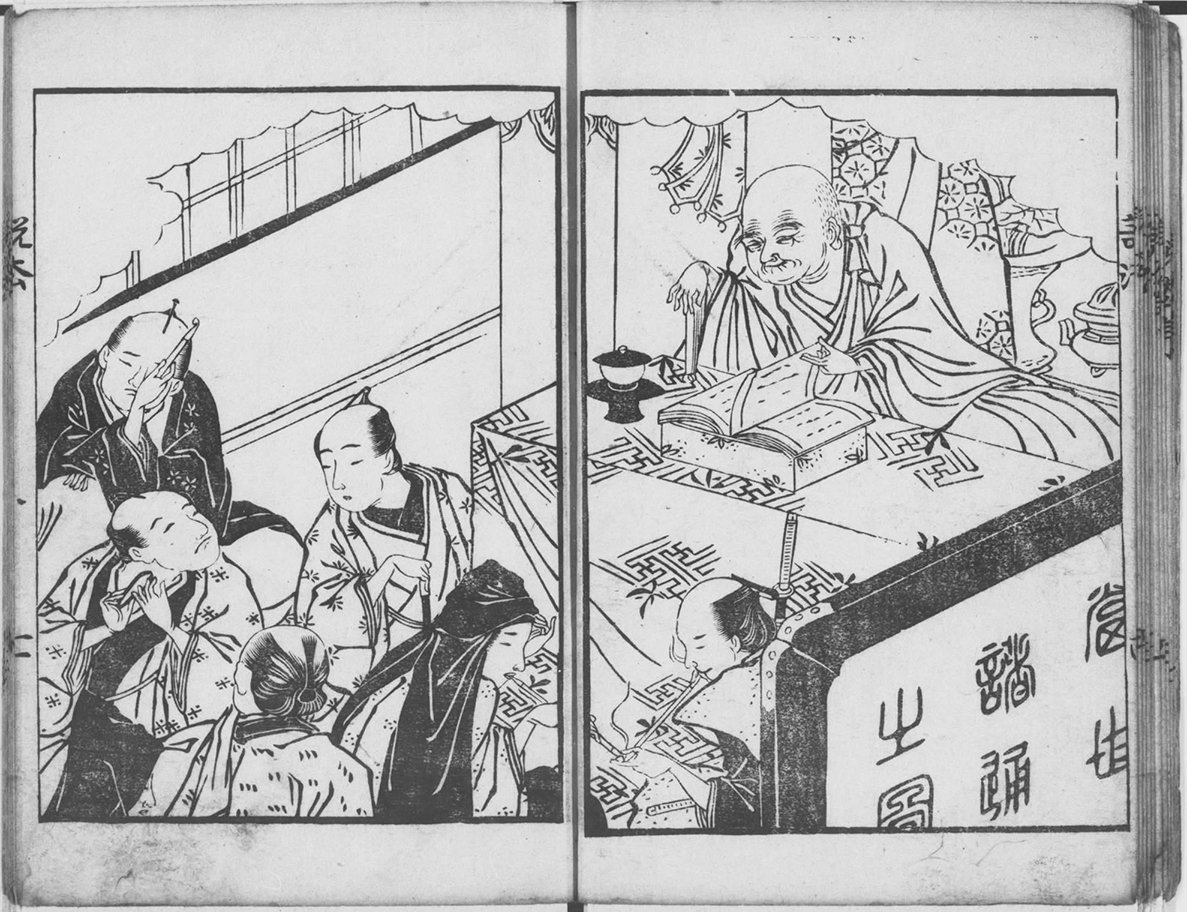
杜選大和尚の説法の場面。聞く側も通ぶって、脂下がりで(気取って)キセルを立てて吸ったり、細い本田髷(ほんだまげ)や頭巾(ずきん)姿でキメたりと“通”修行に余念がない。
東京都立中央図書館所蔵 出典: 国書データベース https://doi.org/10.20730/100101746
このところ、大通大通と称して、まぎらわしい邪宗大通(大通についての誤った教えを吹聴することを、仏教の宗派にたとえて言う)が流行し、自身も若いときにはだまされていたと往時を回想して、大和尚が以下のように述べます。
要約すれば「身なりをキメて、廓の遊びを知り尽くすのが大通だといっぱしに思っていたが、しょせんは井の中の蛙だった」と。かなりの遊び人だったようです。しかしそのうえで、大通とはそんなことではないと語るのです。
「真の大通というのは外見ではなく、浮世の諸事を知り尽くし、あらゆる芸事に通じていてもひけらかすことなく、人の心をのみ込んでそれに合わせて相手を立ててやることができる心意気の人をいう」と言います。
さらに「嘘偽りがあることを前提に身を売っている女郎にわずかの金で誠を見せてもらおう、恋仲になろうなどとは、百両の富くじに当たろうというようなもので、モテたいばかりに見栄を張ったり、なんとか気を引こうと汲々としたりしていると楽しむはずの遊びが苦しみになってしまう」と看破します。
そして結論として、「“真の大通買い”の極意は、あれこれ策を考えたりしていないようでその実、気が利いて、見栄えなど意に介さないようでいてさりげなくツボをおさえている、というもの」だと言うのです。
自己アピールは控えめに、さりげなく相手の意を汲んでふるまうとは、今にも通じそうな処世術……。女郎にもてるのは諦めよとは、まさに、粋の美学を論じて有名な、昭和初期の哲学者・九鬼周造『「いき」の構造』そのもの。彼は「いき」とは「諦め」、つれない浮世の洗練を経て垢抜けし、執着を離れた心だと論じています。
もちろん“春町坊杜撰大和尚”という人物は作中の虚構ですが、ときに作者春町は数えで36歳。そうとう遊び倒して得られた哲学が反映されているようです。

草双紙の歴史にその名を残す鱗形屋と春町・喜三二
ドラマで蔦重が春町に提案した“100年先の江戸”というアイデアは次回以降、蔦屋重三郎版の作品として結実するはずですが、このアイデアもじつは、前に刊行した春町自身の作品の発想を継承したものだということが指摘されています。
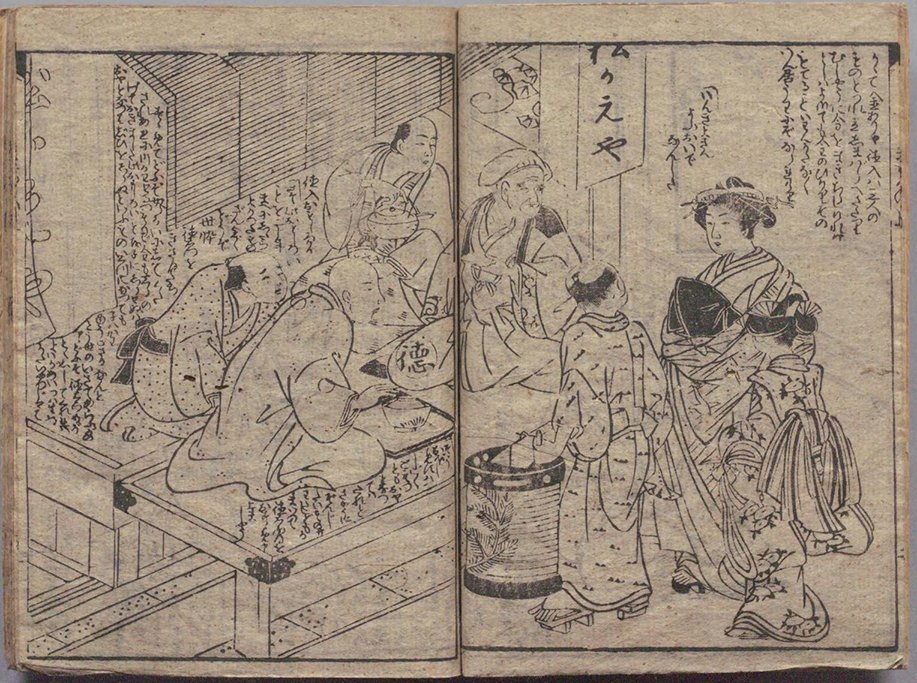
遊女に見惚れる隠居。
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892437
その作品は、特徴的な絵と文字で描かれ、無署名ながらおそらく春町作とされる黄表紙『間違郭輪遊』。隠居した老人が70歳を過ぎて遊里の遊びに目覚め、堅物の息子に勧めたものの、息子が消極的なので勘当してしまう……云々という、“あり得ない”ストーリーの物語です。そもそも100年先の江戸として描かれるのは、とんでもなく“あり得ない”未来です。つまり、『間違郭輪遊』の“あり得ない”話が、100年先の江戸という構想につながってゆくのです。
春町の作品は、喜三二にも多大な影響を与えています。まさに今回のドラマで、“まあさん”こと喜三二が夢に着想を得て書いた『見徳一炊夢』が、青本番付『菊寿草』で極上々吉の評価を受けていました。この本も、同じ夢ネタである春町の『金々先生栄花夢』に触発されたものと考えられています。
ドラマではあまり描かれていませんが、喜三二は春町とともに鱗形屋で多くの仕事をしていました。安永6年、道陀楼麻阿の名で、吉原を地理書の体裁で描いた『娼妃地理記』を蔦重版として出していますが、同じ年、朋誠堂喜三二の名で、鱗形屋から一気に黄表紙6点(春町の挿絵)を出しているのです(ちなみに朋誠堂喜三二の筆名は、「干せど気散じ」=貧乏でも気楽だ、というダジャレです)。
今回のドラマでは、鱗形屋の赤本『塩売文太物語』が、本屋蔦重の原点だったという感動の昔話も披露されました。このように鱗形屋は草双紙の歴史とともにあり、「黄表紙」がジャンルとして確立するにあたって、春町・喜三二を支えた重要な版元だったのです。

参考文献:
水野稔校注『日本古典文学大系59黄表紙洒落本集』(岩波書店 1958)
中山右尚「間違曲輪遊」項『日本古典文学大辞典』第5巻(岩波書店 1984)
井上隆明『喜三二戯作本の研究』(三樹書房 1983)
『洒落本大成』第6・8巻(中央公論社 1979・1980)
加藤定彦『俳諧の近世史』(若草書房 1998)
中村正明「春町作黄表紙の成立考」『國學院雑誌』第124巻第4号(2023)
小池正胤・宇田敏彦・中山右尚・棚橋正博校注『江戸の戯作絵本1・3』(ちくま学芸文庫 筑摩書房 2024)
法政大学文学部教授。日本近世文芸、18世紀後半~19世紀はじめの江戸文芸と挿絵文化を研究している。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。2003年に第29回日本古典文学会賞、2023年に第17回国際浮世絵学会 学会賞を受賞。著書に『天明狂歌研究』(汲古書院)、『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫)、『へんちくりん江戸挿絵本』(集英社インターナショナル)など。




