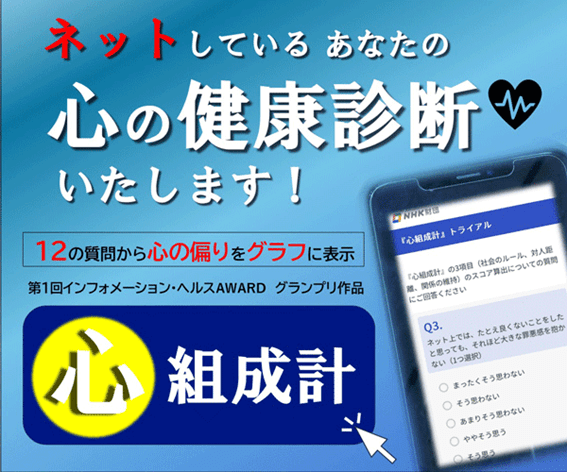“保元の乱”の勝敗を決したのは、「相手側の本陣に放火するかどうか」という焼き討ち、つまり“夜討ち”を実行したかしないかでした。
この作戦は天皇側でも上皇側でも立てることは可能でした。作戦を立てたのは天皇側では義朝、上皇側では為朝であり、天皇側では信西の賛成によってこれが採用され、一方の上皇側では頼長のつよい反対によって否決されました。
なぜ頼長はこれほどつよく反対したのでしょうか。クールな彼には、ある意味ひきょうではあるが、「焼き討ちをすれば勝てる」という見通しはあったはずです。
にもかかわらずこの作戦をしりぞけたのは、頼長なりに、
・これからの日本社会の変化
・その変化をもたらす“武士”という“もののけ(化けもの)”の出現
という現状認識があったからではないでしょうか。
そしてそういう社会が実現した際に、
「自分の属する藤原摂関家はどうなるのか」
という予測を立てたのだと思います。
まだ形にはあらわれていませんが、ぼくは清盛の考えた日本の政治形態は、「天皇親政」だったと考えます。
ということは、「院政と摂関制の廃止」につながります。天皇を頂点に公家も武士も天皇のけらいとして、平等にしごとをする朝廷の実現を目指したのです。

平家がのちにほろびるのは、清盛が武士の原点を忘れて公家になり、しかも摂関家同様となってしまうからです。
このときすでに頼長には、
・ほろびるのは藤原家であり、自分自身だ
・そしてそういうおそろしい力を発揮するのは武士だ。清盛や義朝に違いない(残念だが為義・為朝にはその力はない)
というような予測があったのではないでしょうか。
その意味で“夜討ち”作戦をしりぞける頼長は、「予測されるほろびの道へのスタート」を切ったのです。
「平家物語」の基調音は“ほろびの悲哀感”ですが、平家だけでなく、その前奏曲としての頼長の悲しい決断にもぼくは、
「ほろびゆく者の哀しさ」
を感じるのです。頼長の決断は「武士をこれ以上のさばらせない」という意思表明でした。
(NHKウイークリーステラ 2012年6月1日号より)
1927(昭和2)年、東京生まれ。東京都庁に勤め、広報室長、企画調整局長、政策室長などを歴任。退職後、作家活動に入り、歴史小説家としてあらゆる時代・人物をテーマに作品を発表する。