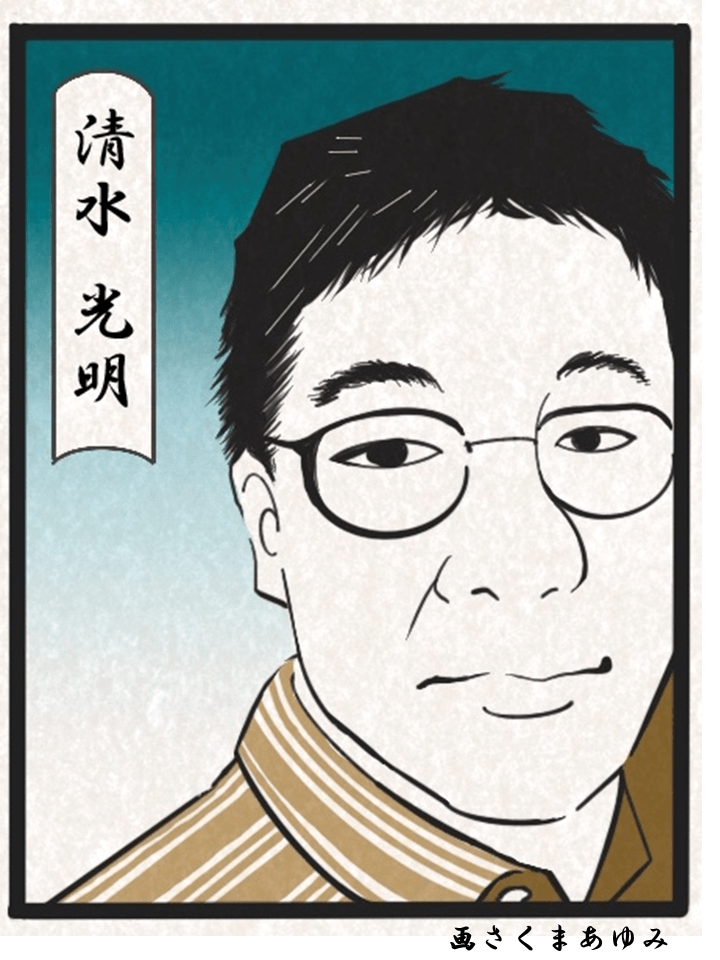今回は、政治の世界でまた大きな出来事がありました。将軍世子(跡継ぎ)・徳川家基(演:奥智哉)の急逝と、“白眉毛”こと老中首座・松平武元(演:石坂浩二)の逝去です。両者は50歳近く年が離れていますが、たまたま同じ安永8(1779)年に亡くなりました。
ドラマでは、その辺りをミステリー仕立てにして、両人が何者かに毒殺されたというストーリーが展開していきました。これは、史実とは大きく異なりますが、ついそういう風に説明したくなってしまう構図や雰囲気がじつは当時からありました。
本コラムでは、家基と武元が逝去した経緯、他の老中たちの相次ぐ逝去などが田沼意次(演:渡辺謙)に与えた影響や、当時から流布していた意次による暗殺説の内容・背景などをたどっていきます。
家基は、第10代将軍・家治(演:眞島秀和)の長男で、第11代将軍への就任を期待されていました。ところが、安永8年2月、新井宿(現・東京都大田区山王辺り)へ鷹狩りに行く途中、東海寺で休憩した際に体調を崩して亡くなりました。享年18。
同年7月、武元も病気で逝去しました。享年67。じつは、この時期に亡くなった老中は武元だけではありません。意次が安永元年に老中に就任したとき、老中は5人いました。ですが、その後、安永8年から天明元(1781)年のわずか2年半のあいだに4人が亡くなりました。前述の武元、安永9年6月の板倉勝清、同年11月の阿部正允、そして天明元年9月の松平輝高(演:松下哲)です。
かくして老中は、天明4年5月までは、首座の松平康福(演:相島一之)、意次、新任の久世広明の3人。常時5~6人が定員の老中は、しばらく3人体制になりました。
側用人を兼帯(兼任)しており、家治の信任が厚かった意次を抑えられる老中は、康福だけです。ただ、康福の娘は、意次の嫡子・意知(演:宮沢氷魚)に嫁いでいました。広明の孫も、意次の外孫(他家に嫁した娘から生まれた子)の結婚相手でした。
こういった縁戚関係を一つの背景として、意次は息子の意知を「部屋住み」(家督相続前の状態)のまま奏者番(幕府の儀礼を司る役職)に就任させ(天明元[1781]年12月)、さらには若年寄(幕府内部を管轄する要職)に昇格させます。このような異例の人事を行った(同3年11月)のも、この老中3人体制の時期でした。
そんな権力構造の下では、意次の権勢が一層高まっていきます。下総国印旛沼開拓工事、蝦夷地開発、貸金会所構想など、田沼色の強い政策が打ち出されていったのも、ちょうどこの時期です。
当時から意次による家基の暗殺説や老中たちの相次ぐ逝去への関与の風聞が流布していたのも、これが一つの背景でした。どんな内容なのか見てみましょう。
意次の息のかかった医師が毒薬を処方!?
前述の武元の右筆(秘書役)を務めた儒学者・石井子彭が著した『続三王外記』(寛政初[1789]年頃成)という書物(写本で流布)には、次のように記されています。
さらには、前述の武元や勝清の相次ぐ逝去についても、次のように述べています。
医者や狩りを利用しながら、病死に見せかけて将軍世子や老中を排除する――。今回のドラマにも出てきそうな恐ろしい内容です。
ちなみに、池原雲伯(良誠)はドラマには登場しませんが、実在の奥医師です。安永5年から、家基の侍医を勤めています。雲伯については、『虚実夢物語』(あるいは『実説夢物語』。寛政初年頃成)という筆者不明の写本に、次のようなことも書かれています。
これも、ドラマにできそうな不気味な話です。この時期の尾張藩主は、徳川宗睦。彼をも亡き者にしようとした意次は、やはり雲伯を送り込むが、今回は斬られて死亡するという筋立てです。実在の雲伯は、天明5年7月には亡くなったようなので、この話には少なからず齟齬があります。
久世大和守は前述の老中・久世広明、依田豊前守は大目付(大名・幕政を監察する役職)を勤めた旗本・依田政次のことで、両者は天明5年、同3年に亡くなっています。彼らにも、毒殺疑惑が浮上していました。
将軍世子と老中たちの相次ぐ逝去と老中3人体制、そして田沼政治の積極的展開――。この状況を苦々しく見ていた人たちからすると、意次や雲伯によって毒殺などの狡猾な手段が次々に行われてこんな状況になったという説明は納得しやすかったのではないでしょうか。
古今東西の陰謀論やその形成過程と比較してみると面白いかもしれません。
参考文献:
辻善之助『田沼時代』(岩波文庫)
藤田覚『田沼意次』(ミネルヴァ書房)
山本博文『お殿様たちの出世 江戸幕府老中への道』(新潮社)
『寛政重修諸家譜 第22』(続群書類従完成会)
東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。