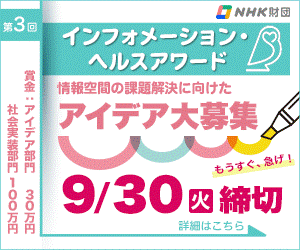鶴屋喜右衛門は、江戸で大衆本の出版を取り仕切る地本問屋のリーダー的存在だ。仲間の鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)が偽板事件で捕まった間隙を縫って、蔦屋重三郎(横浜流星)が板元に参入しようとするが、鶴屋はどう対抗するつもりなのか。演じる風間俊介に聞いた。
大河ドラマに出演するのは、日本代表チームに選抜されたような感覚で、喜びを感じると同時に身の引き締まる思い
——「べらぼう」の出演オファーを、どのように受け止めましたか?
大河ドラマが大好きだった亡き祖父、そして父への親孝行にもなるので、とても光栄に思いました。大河ドラマは、オープニングでテーマ曲が流れると、出演者の名前がドンッと大きくクレジットされるじゃないですか。素敵な役者さんたちに混ざって自分の名前が出てきた瞬間というのは、日本代表チームに選抜されたような気持ちになるんです。
これまで大河ドラマには、幕末(「西郷どん」)、戦国(「麒麟がくる」)と出演させていただきましたが、それぞれ魅力的な時代でした。今回は、2年前に出演させていただいたドラマ10「大奥」と同じ江戸中期が舞台で、同じ森下(佳子)さんの脚本ということで、大きな喜びを感じると同時に、地に足をつけて演じなければと、身の引き締まる思いがしました。

——森下さんの脚本の面白さは、どこにありますか?
描かれる歴史のうねり自体も面白いですが、時代の流れに翻弄される人々の思いがしっかり描かれているところが好きです。森下さんの作品は、登場人物がどんなに泥にまみれても、泥くさいだけでなく、繊細かつユーモラスに描写されているので、脚本を読むたびに「おしゃれだなぁ」と感じます。
戦国時代が終わって、江戸の平和な時代になってからは、商売が戦の代わりになったと思うんです。「べらぼう」のなかで繰り広げられる“商いの戦い”が現代日本の状況に重なったり、視聴者の皆さんが蔦重や鶴屋を自分に重ねたりする瞬間があるのではと、楽しみにしています。
蔦重の才能を認めつつも、鶴屋には「よそ者が地本問屋の結束を乱すことは許さない」という信念がある
——鶴屋喜右衛門の描かれ方には、どんな印象を持ちましたか?
蔦重と対立する構図にはなっていますが、鶴屋は間違ったことは言っていません。蔦重の視点に立つと、鶴屋は目の前に立ちはだかる邪魔な存在ですが、一方の鶴屋の人格や正義がゆがんでいるかというと、そんなことはなくて、人としての筋を通す健やかな人物です。そこがキャラクターとしても、物語の中の役割としても素敵だと思います。
蔦重は本を「作ること」に情熱を注いでいますが、鶴屋は作った本を「広める」ことに重心を置いているように感じます。だからこそ、本を広めるために必要な“地本問屋の結束”を、よそ者が乱すことは許さない、という信念を持っているのだと思います。
憎まれ役になるとかヒール(悪役)を演じるとかではなく、「私には私の正義がございます」という、強い信念を持った人物でいたいと考えています。その信念が強固であれば強固なほど、蔦重側から見たときに、鶴屋が曲者に、そして大きな壁になると思うので。
——鶴屋は、蔦重のことをどのように見ていたと思いますか?
鶴屋は優れた商人なので、初めて蔦重に会ったとき、その才能にビビッドに反応しただろうとは思います。ただ、「こいつはすごい」と思っても、吉原の人間が地本問屋の仲間に入る道筋を認めてはいけないと判断したんでしょうね。

――蔦重の才覚そのものは評価しているわけですね。
蔦重がやるようなことは鶴屋にはできません。だから、その才能は欲しいでしょうし、憧れや羨ましさを感じていたと思います。
老舗と、ベンチャーのユニコーン企業の違いみたいなところがありますよね。老舗だからできることもあれば、老舗にはできないこともあって……。蔦重側からの、「自分たちに地盤があったら。資本があったら……」という思いが描かれていますが、鶴屋側から見たら、「身軽だったら。歴史に縛られなかったら……」という思いもあるんです。究極の“ないものねだり”ですよね。
——鶴屋がもともと上方に地盤があったことは、蔦重を認めないことに関係していますか?
いえ、上方発祥ではありますが、僕が演じる当代の鶴屋は、「江戸で生きていく、江戸で商いを大きくしていく」覚悟のある人物だと捉えています。
もちろん先代たちが打ち立ててきた偉業に敬意は持っています。でも、自分が江戸で新しいページを描くと決めたときに、もはや上方のことは意識しなくなっていると思います。江戸ことばを使うのは、江戸に骨をうずめる覚悟からでしょう。
自分のミッションは「江戸の出版界で天下を取ること」だと、鶴屋は考えていると思います。

——地本問屋をまとめる立場ですが、ほかのメンバーとの関係性をどう思いますか?
鶴屋はいつも「私は皆さんと対等です。序列を気にするのはやめましょうよ」というスタンスでいます。傍若無人に「俺のところが一番大きいんだから、お前たちは言うことを聞いていればいい」と、ワンマンで手腕を振るったほうが、ほかの地本問屋の皆さんは楽なんでしょうけど、鶴屋は「一緒に手を取り合って」なんて言うんです。食えない存在ですよね(笑)。
僕自身の気持ちとしては、(西村屋与八役の)西村まさ彦さんも、(鱗形屋孫兵衛役の)片岡愛之助さんも尊敬している先輩なので、一緒に並んでいるだけでとてもうれしいですし、勉強になっています。それが、「いえいえ、私は若輩者で」という鶴屋の気持ちとリンクして、「あいつは謙虚だけど、食えないな」という空気になったらいいな、と思っています。
でも、実在の人物を演じるということは、その人物にゆかりのある方たちの目に触れる可能性がある、ということです。鶴屋喜右衛門にゆかりのある方々にも物語を楽しんでもらいたいので、憎まれつつも、皆さんから好かれる役になったらうれしいですね。
自由で軽やかな蔦重と、歴史の重みに縛られる鶴屋。そんな対比が見せられたら
——蔦重役の横浜流星さんとお芝居をされて、どんな印象を持ちましたか?
軽やかに演じていらっしゃいますね。それこそ、見とれてしまうような佇まいで……。蔦重は自由で軽やかに動き回るけど、鶴屋は歴史の重みが枷となって決まった動きになってしまう。そんな対比で、「明確に違うふたり」として見えたら面白いと思っています。
——所作で意識しているところはありますか?
鶴屋は、今でいう大企業のトップなので、立ち居振る舞いは“たおやか”でありたいと思っています。洗練された、と言いましょうか。ちょっとした指先の動きがきれいだといいなぁ、と考えていて、そのへんを所作指導の花柳寿楽先生に教えてもらっています。

——撮影現場で驚いたことはありますか?
美術部の仕事ぶりが突出していますね。セットには「もう建造物じゃん!」と思うくらいの作り上げられた世界観があるので、現場に入ったときに「これは生半可な覚悟では弾き飛ばされてしまう」という凄みを感じました。
——「べらぼう」ならではの面白さとは何でしょう?
大河ドラマに吉原が登場して、それを正面から、そして優しく描くところに大きな魅力を感じます。
現代には「吉原」という住所は存在しなくて、残っているのは「吉原大門前」という交差点の名前くらいです。それでも、「吉原に行く」と聞けば、それが何を指しているかが今でもわかる。江戸時代が終わって何年も経つのに、感覚としての「吉原」が残っているというのはすごいことですよね。
鶴屋と同じように、「吉原は品性がない場所で、公序良俗に反する人々が集まっている」と捉える方もいらっしゃるでしょう。だけど、そこには懸命に生きている人たちがいるわけで……。
世間から差別され、日々戦っている人が、今も日本にはたくさんいると思います。そういう人たちの心に、蔦重という主人公を通して光がさすような物語になったら、と願っています。