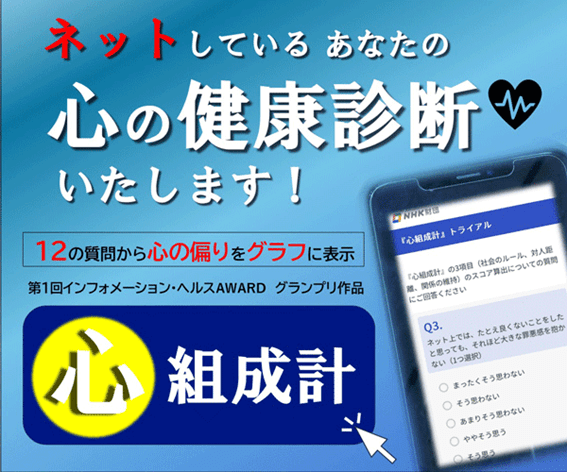いよいよ決戦の嵐がちかづいてきます。皇室では後白河天皇と崇徳上皇の対立があり、摂関家では藤原忠実・次男頼長父子と長男忠通の対立が、さらには、かつての鳥羽院の中宮・待賢門院と美福門院の対立の余波などが、この時期に一丸となって爆発寸前となりました。
しかし、ここにあげた対立グループが、具体的な勝敗の頼みにしたのが武士であり、その武力(暴力)です。
おもしろいのはその武士たちの反応です。すでに平氏は平氏、源氏は源氏というように、氏族単位でのグループとしてまとまりかけてはいましたが、この対立では必ずしもひとつにまとまりませんでした。

平氏でも、清盛は天皇側に、頼盛は最初上皇側に味方しようとします。源氏では為義が上皇側に、子の義朝が天皇側につきます。
つまり、一族でもそれぞれ味方する対象がちがうのです。この現象は一族の結束力が不足していた、というよりもぼくは、「それぞれの武士“個人”としての決断」があったと思います。
ということは、このころはまだまだ、「組織(氏族とか武士団とかいうもの)よりも、個人の決断」が重んじられていたのだ、と思います。
ことばをかえれば、武士にも、「人間としての思考の自由」があったのです。貴族が、“番犬”としてバカにしてきた武士にも、「考える力と結論を出す力(判断力・決断力)」が身についていたのです。貴族はこれを見落としていました。
さらにこのとき、「どっちに味方するか」の判断に、清盛や義朝は、「これからの世の中(社会)はどうなるのか。その主導力をにぎるのは後白河なのか崇徳なのか」という、世を見通す“先見の力”ももっていました。もう“犬”ではなかったのです。
(NHKウイークリーステラ 2012年5月25日号より)
1927(昭和2)年、東京生まれ。東京都庁に勤め、広報室長、企画調整局長、政策室長などを歴任。退職後、作家活動に入り、歴史小説家としてあらゆる時代・人物をテーマに作品を発表する。