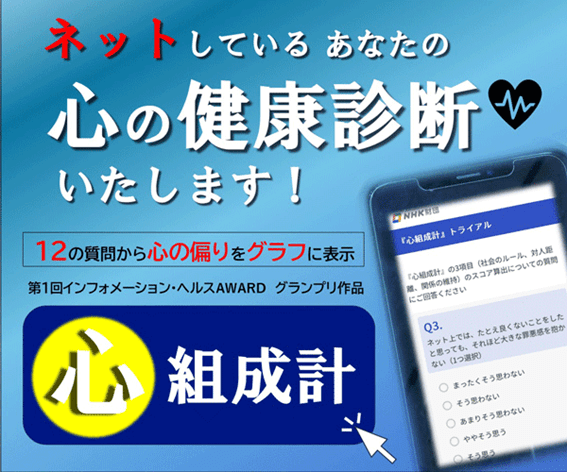〈第2回のあらすじ〉
静(吉岡里帆)と純介(笑福亭鶴瓶)は、出席したスマートシティー化計画の説明会に開発業者の一員として圭一(中島裕翔)が現れ驚く。住民からヤジが飛び交う中、いきなり圭一が「子どものころランドセルを手放せなかった」と思い出話を語りはじめ……。
共に周りから「空気を読め」と言われていたことに共感する静と圭一。そして圭一は、静と純介をクラシックの演奏会に招待する。
「自分のとっての“あたりまえ”は、他の誰かにとってはそうではないかもしれない」
そんな発想の転換こそが、誰もが暮らしやすい共生社会を実現するのではないか――。
「しずかちゃんとパパ」第2回を見て、ふとそう思った。
「土曜日の午後、空いてますか?」
ある思いから、静と父・純介をクラシックの演奏会に誘う圭一。
「あ、無理です、父は。全然聞こえないんで、音楽は」
淡々とした口調で、あたりまえのごとく圭一の誘いを断ろうとする静。
それに対し、まっすぐな瞳で問いかける圭一が印象的だ。
「聞こえないと、音楽は無理なんですか?」
この何気ないひと言は、静だけでなく、画面越しに私たちにも問いかけてくる。
“音楽は耳で聴いて楽しむもの”という考え方へのアンチテーゼともとれる。
一方、地元の小学校教員である鈴間さくら(木村多江)もまた、純介に音楽会の撮影を依頼したことに対し、モヤモヤを隠せずにいた。
「耳の聞こえない純介を音楽会に誘ったのは無神経だったのではないか……」
音楽を教える教員だからこそ“音楽は耳で聴くもの”という固定観念に縛られ、一方的な不安を抱えしまったのだろう。
確かに、音楽は耳で聴くものだ。
だが、耳で聴くだけがすべて、ではない。
そして、“あたりまえ”と信じて疑わなかった静の世界は、ミュージックホールに大きな風船を持って現れた圭一によって、一瞬でひっくり返される。
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/610/
▼聞こえない人に「音」を届けたい ー小さな機器にかける技術者ー
https://www.nhk.or.jp/heart-net/program/rounan/416/
ところで、日本の伝統芸能である狂言*には、「視覚障がい者(座頭*)」を主人公とするジャンルが存在する。
その中でも、古くに成立したと考えられる「猿座頭」という曲の会話を見てみよう。
(花見というのは、目があってこそ出来るものでしょう。あなたは目が見えないのに)
夫「愚かな事を云、花は、嗅いだも見たも、同じ事じや」
(愚かなことを言うものだ。花というのは、その香りを嗅ぐのも見るのも同じことだよ)
――狂言「猿座頭」/和泉流 天理本(1646年頃成立)より
目の見えない夫(座頭)と目の見える妻が、花見に行こうか行くまいか、と会話するシーン。
この妻は、目の見えない夫を花見に誘うことをちゅうちょしていた。
だからこそ、上記のように「目が見えないのに花見なんて」という言葉が出てきたのだろう。
やはりここでも、「花見=目で見るもの」という“あたりまえ”が作用している。
ところが、私が驚いたのは、夫の返しである。
「花は、目で見るだけではなく、鼻で香りを嗅ぐこともできるだろう」と、強気に言うのだ。
「花見」という単語を、その字の表すとおりに解釈していた私は、このひと言との出会いによって、自分の中に横たわる固定観念とぶつかった。
花見で香りを嗅げばいいじゃないか、というのはへ理屈のように聞こえるだろうか。
けれど、これを言った張本人にとっては、それが「花見」のあり方なのだ。
「目で見るだけが花見ではない」――視覚障がい者が気づかせてくれた、「発想の転換」の妙だ。
さて、ドラマ終盤、静はこう口にする。
「思い込んじゃってました。聞こえないから、音楽なんて無理だって」
自分にとっての“あたりまえ”を疑うこと――。
そんな発想の転換が、誰かの“あたりまえ”を知ることにつながるのかもしれない。
*狂言…中世の喜劇。笑いを通して、人間の普遍的なおかしさを描きだす
*座頭…江戸期における盲人の階級名のひとつ
1998年、東京都生まれ。大学院では「狂言に描かれる障がい者像と笑い」について研究。身体性別による差別と、それを取り巻く社会構造についても大きな関心を寄せる。女性の人権活動に多数参加。