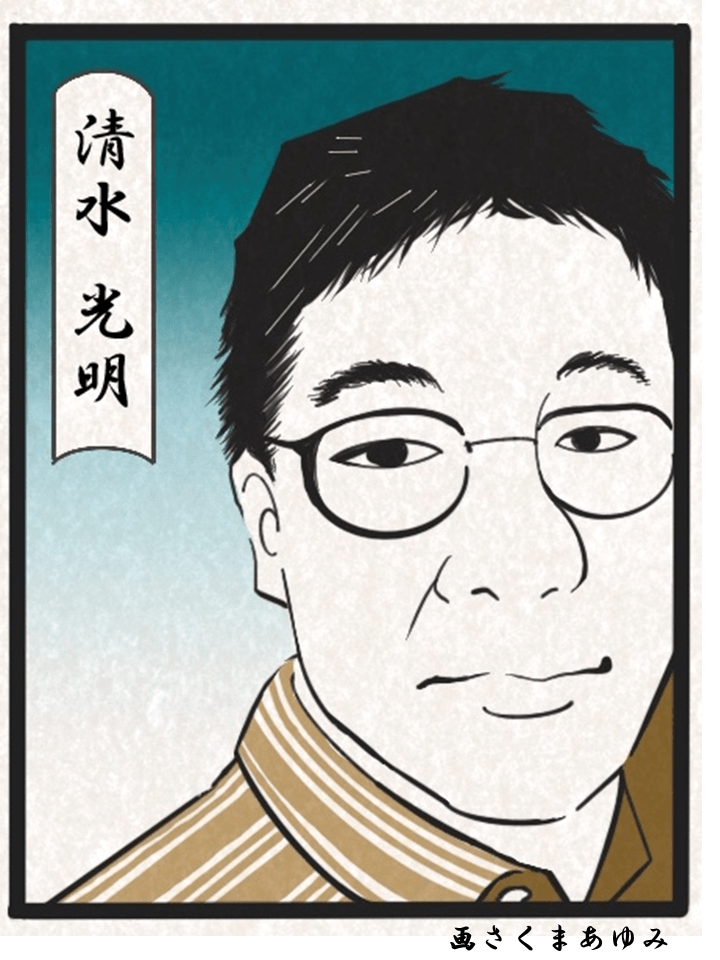ついに大きな事件が政治の世界で起こってしまいました。天明4(1784)年3月24日の田沼意知(演:宮沢氷魚)への刃傷事件です。下手人は、旗本(知行は500石)で新番組(幕府・旗本の軍事組織である五番方の一つ)の番士・佐野政言(演:矢本悠馬)。ドラマでは、以前から、丁重な物腰ながらどこか不気味な雰囲気を漂わせていました。
そして、今回、屋敷の桜が咲かないことに苛立つ老父の政豊(演:吉見一豊)に涙ぐみながらも微笑んで、「父上、私が!……私が咲かせてご覧にいれましょう」と覚悟を決めた後でこの挙に及びました。
他方、旗本で勘定組頭(勘定奉行の下僚)の土山宗次郎(演:栁俊太郎)の名前で身請けされ、吉原を何とか脱出できた誰袖(演:福原遥)ですが、その矢先に肝心の“花雲助”こと意知の事件が発生したということになります。おそらく次回、誰袖はその衝撃の知らせを聞くことになるでしょう。
ちなみに、この意知・宗次郎・誰袖が絡む身請けのエピソードは、天明4年頃に宗次郎が総額1200両で大文字屋の誰袖を身請けしたという話から想を得たフィクションです。意次の腹心で蝦夷地の調査を行っていた宗次郎が、当時如何に羽振りがよかったかがよく分かります。のちに、彼は勘定組頭だったときに公金を横領していたという疑いが発覚しますので、上記の1200両にはそういう不正な手段で得たお金も含まれていたのかもしれません。
さて、意知刃傷事件は、今回と次回のドラマ2回にわたって取り上げられます。そこで、コラムも2回に分けて、事件の経緯や、政言の動機についての諸説、そしてこの事件が社会や政治に与えた影響などをたどってみたいと思います。
政言の犯行動機は私怨か? 公憤か? 乱心か?
奏者番(大名らが将軍に拝謁する際、儀礼進行を司る役)を勤めていた意知は、天明3年11月、引き続き“部屋住み”(家督相続前の状態)のまま若年寄に昇進しました。これは、前例のない人事です。さらに、その際、ときおり奥勤め(将軍家の奥向きに勤めること)をすることも命じられました。この結果、父・意次(演:渡辺謙)は奥兼帯(奥勤め兼任)の老中で、息子の意知は奥兼帯の若年寄となりました。
この人事は、異例の老中3人体制(コラム#15参照)が続くなかで、田沼家の権勢を一層強く示し、さらにはその権力を意次から意知へ継承することを企図していました。ドラマのなかでも、こういった出世やさまざまな出来事を経験して、初々しいところは残しながらも父親と同様に、清濁併せ呑む政治家へと次第に変貌していく意知の姿が描かれていました。
ただ、これは、いわゆる“親の七光り”そのものです。不満を抱いた人々は少なくありませんでした。
そんななか、天明4年3月24日の午後1時頃、事件は江戸城内新番組の詰所前で起こりました。江戸城から退く途中でこの場所を通りかかった意知に対して、警備のために詰めていた政言が突然斬りかかりました。当時、そこには大目付・目付・勘定奉行以下16名もの役人がいましたが、政言は意知だけを斬りつけました。意知がターゲットであったことは明らかです。
今回のドラマで描かれたのは、ここまででした。では、政言は、どうして意知に斬りかかったのでしょうか。これについては、いくつかの説があります。
第一は、私怨説です。ドラマではアレンジされて描かれていましたが、意知に頼まれて佐野家の系図を貸したのに幾度催促しても返してくれなかったこと、天明3年12月の将軍・家治御成の鷹狩りの際に、政言が鳥を仕留めたにもかかわらず意知がそれを認めなかったことなど、いくつかの怨みが積み重なって犯行に及んだという説です。ただ、この根拠になっている史料は偽文書のようです。
第二は、公憤説です。すなわち、父の意次は老齢だが、子の意知はまだ若く今後も改革を続けるであろうから意知を殺さなければならない……。権勢を振るう田沼親子を憎む人々はこのように考えて、政言がそれを実行したとする説です。これは、当時、オランダ商館長だったイサーク・ティチングの見解です。事件に対する同時代人の認識という点では一定程度参考にはなりますが、信憑性のほどは不明です。
第三は、乱心説です。これは幕府評定所の公式発表でしたが、公式の見解だからと言って鵜呑みにすることは危険です。
このように、いくつか政言の動機についての説はありますが、結局のところ現時点では真相は分かっていません。
今もなお謎だらけの事件ですが、次回のドラマで事件の顛末はどのように描かれるのでしょうか? また、意知の安否は? それを知った誰袖の反応は? 気になることばかりですが、それは次回のドラマまで待つことにいたしましょう。
参考文献:
浜田義一郎ほか編『大田南畝全集 第2巻』(岩波書店)
大石慎三郎『田沼意次の時代』(岩波書店)
藤田覚『田沼時代 日本近世の歴史4』(吉川弘文館)
藤田覚『田沼意次』(ミネルヴァ書房)
辻善之助『田沼時代』(岩波書店)
東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。


![べらぼうコラム #27 佐野政言による田沼意知刃傷事件の経緯と動機 その後の社会・政治に与えた多大な影響とは?[前編]の画像](https://www.steranet.jp/wp-content/uploads/2025/12/7a0dcd13f8d3251d5a149a1255ac7996.jpg)