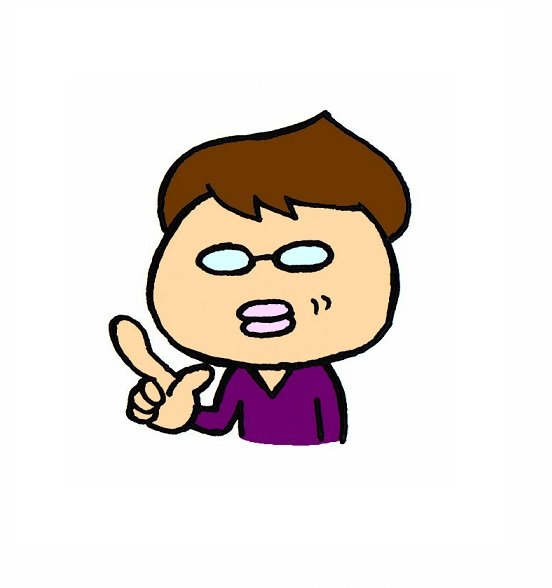
直秀(毎熊克哉)の鳥辺野事件でむせび泣く皆さん、花山天皇(本郷奏多)騙し討ち失墜に憤る皆さん、いかがお過ごしでしょうか。いちいちロスになっている場合じゃない。もうこれからもどんどん恨みと呪いと嫉妬が渦巻く様相の「光る君へ」。
右大臣・藤原兼家(段田安則)の一家がいかに嫌われているかがよくわかる顛末であり、憎まれっ子は世にはばかるという現実でもあり。兼家は謀によって花山天皇を追い出して自らが摂政となり、多くの人に恨まれて呪われながらも、ますます勢いづいてきたところだ。

まひろ(吉高由里子)と藤原道長(柄本佑)の恋模様が激しく揺れて動いた3月、今回のテーマは「妾」。不倫しようものなら世間につるし上げられる令和とは異なり、この時代はどんなに貧乏な貴族でも妾がいて当たり前。妾がどう描かれているのか見ていこう。
余命僅かの妾を看取る為時に感動するまひろ

まひろの父・為時(岸谷五朗)は妾宅へ詰めている。乳母のいと(信川清順)は為時を思慕しているため、快く思っていない様子だが、まひろは気になってしょうがない。カタブツの父がこれだけ入れ込むのはどんな女か、わざわざ覗きにいく下世話なところもいい。以前、姫サロンで『蜻蛉日記』が妾の矜持を書いたものだと指摘していたまひろは、妾についてはどう考えているのか。
そもそもまひろは正妻の娘であり、亡くなった母・ちやは(国仲涼子)への思いも強い。うだつがあがらないくせに妾宅へはいそいそと出かけていた父、そんな父が出世できるよう、文句ひとついわず、密かにお百度参りをしていた母。優しくて慎ましい母よりも、魅力のある女だとすれば興味もわく。

ところが、好奇心で妾宅へ行ったものの、高倉の家はとんでもなくみすぼらしく貧しいあばら家だった。父の妾・なつめ(藤倉みのり)は病弱で、どうやらもう長くはないことがわかる。
そこで寄り添って懸命に看病する父の姿を見て、まひろは「胸が熱くなりました。父上はご立派でございます」と感動するのだ。なつめの身の回りの世話を申し出るも、「それは気詰まりだから」と断る為時。そりゃそうだ。亡くなったとはいえ、正妻の娘に面倒を見てもらうなんて、妾にとっては針の筵ってもんよね。
なつめの最期には、なつめの実娘・さわ(野村麻純)を会わせてあげる為時&まひろ。さらには、さわを妹のように可愛がるまひろ。寛容と言えば寛容だが、それは父の妾だからだ。そして、この「妾問題」がまひろの「自分事」になっていく。

夢見がちで熱烈な道長、志を託すまひろ
直秀の無残な死に直面した後、道長とまひろは文のやりとりを重ねていく。丸っこい文字のかなで書く道長は、和歌で熱烈ラブコール。情熱的というかロマンチシズムというか夢見がちというか。結局は世間知らずのボンボンなのよね。
一方、まひろは冷静に美文字の漢詩で返す。道長を恋しく思う気持ちはむしろまひろのほうが強いとさえ思えるのだが、そこを抑えに抑えて、志を託すのである。


文のやりとりを経て、夜の逢瀬を実現するふたり。道長は「藤原を捨てる、遠い国へ一緒に行こう」と駆け落ちを提案(おいおい、夢見る中二病か!)。あまりに非現実的な提案なので、まひろは丁重に断る。せっかく身分の高い家に生まれたのだから、政で頂を目指し、この国をよくする使命があると道長を諭す。
月明かりの下、体を結ぶふたりだが、相思相愛でも結ばれない悲しき宿命。毎晩同じ月を見ているというのにね。そういえば、左大臣家の姫サロンで『古今和歌集』を学んでいるときに、まひろは作者の思いに自分を重ねていた。
この和歌を読んだ姫たちは「おなごは殿御を待つだけなんてもどかしい~」「寝てしまうなんて!」とキャッキャ盛り上がっているが、まひろは「(作者は)寝てはいないと思う。寝てしまったことにしないと自分がみじめになるから」と解釈を披露。常日頃、身分の差による憂き目を経験しているからこそ、恋愛において一番になれないみじめさと、それを打ち消す女の矜持が必要なのだと。
そのせめぎ合いが、実際にまひろの身にも起こる。
駆け落ち案も妾案も却下され、衝動的に結婚宣言
まひろとどうにかなりたい道長は、文を書いて従者・百舌彦(本多力)に託すのももどかしくなって、直接まひろの家へ。まひろの従者・乙丸(矢部太郎)に言付けを頼む。割と直情径行なんだよな、道長は。
それを聞いたまひろも、胸高鳴らせ、逢引の場へ走る。その夜の逢瀬で道長は「妻になってくれ」と言う。喜んだのもつかのま。妻といっても正妻ではない。正妻として迎えることは身分の差で絶対にかなわないものの、妾ならば可能という提案をした道長。まひろは「そんなの耐えられない」と言う。女の矜持である。

第1弾の駆け落ち案も却下、第2弾の妾案も却下、道長はブチ切れてしまう。そして第3弾は、なんと左大臣家の一の姫、つまり源倫子(黒木華)に婿入りすると宣言。心の中ではまひろに「妾でもよいと言ってくれ」と願いながら。半ば、やけっぱちの道長だが、他に打つ手もなく。
まひろにしてみれば、よりによって相手が倫子。姫サロンの主宰者であり、格下のまひろをなにかと気にかけてくれる優しい倫子。「思う人はいるけれど内緒。でも必ず夫にします」と自信満々に断言していた倫子である(もちろん視聴者はとっくにわかっていたけれど、どんな過程を経て婚姻に至るかには興味津々なわけよ)。

衝撃の宣言を受けたまひろは、瞬時に悟る。点と点がつながって線に。右大臣家と左大臣家。権力の中枢である家のふたりの縁談がうまくいかないはずがない。苦しい胸の内を隠して「私は私らしく自分の生まれてきた意味を探してまいります。道長様もどうぞお健やかに」と、自らの恋路を断つのだった。
世間知らずのボンボンと駆け落ちしても地獄、妾になることを受け容れたとしても地獄。たとえ愛する人が足しげく通ってくるとしても、妾道はいばらの道。まひろはその道を自らの意志で拒んだのである。

「妾考」男たちの言い分・息子の観察・女の意地
道長の言い分としては「妾であっても一番に愛する、心はお前にある」。これは友人・藤原斉信(金田哲)がのたまっていた持論を真に受けたふしもある。「家柄のいい女を嫡妻にして、あとは好いたおなごの家に通えばいい」ってやつね。
また、父の親友である藤原宣孝(佐々木蔵之介)は、妾にはなりたくないまひろを諭す。「わしにも幾人かの妾はいるし、身分の低い者もいるが、どのおなごもまんべんなく慈しんでおる。文句を言うものなどおらんぞ。もっと男を信じろ」と。要するに、妾だとしても愛されて、女は十分に幸せになれるという男たちの勝手な理論が正当化されているわけだ。

ところが、妾の息子は異なる見方をしていることがわかる。兼家の妾の息子・藤原道綱(上地雄輔)は、母の寧子(財前直見)をつぶさに観察しているようで。
「自分にも妾はいる。それなりに大事にしているが、妾からすればまるで物足りぬのだ。母を見ていたらわかる。いつ来るかわからない男を待ち続けている。男は精一杯可愛がっているつもりでも、妾は常につらいのだ」という。うつけと思っていたけれど、道綱、案外ちゃんと見ておるな。
寧子、つまり藤原道綱母は『蜻蛉日記』の作者であり、権力者の妾としての心境をこまやかにつづった才女だ。兼家が先妻の息子たちを役職につけていることを知り、自分の息子の道綱も出世させてほしいとさりげなく懇願したりもする。これぞ女の意地、妾の矜持である。

妾道を選ばなかったまひろに、この後訪れるであろう精神的苦痛に今から鳥肌が立つ。悲恋こそ最大のモチベーション、まひろの心情描写に注目しよう。
まったく関係ないが、「妾」という文字が割と好きだ。昔の文学作品では「あたし」とルビがふられて、一人称として使われていた記憶がある。辞書では「わらわ」とされているが、「あたし」のほうがなんとなくしっくりくる。
分解すると、「妾」は自分の足で「立つ女」。「家にいる女」嫁よりも「妾」のほうが、まひろの生きざまに近いなと想像してしまった。
ライター・コラムニスト・イラストレーター
1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業。健康誌や女性誌の編集を経て、2001年よりフリーランスライターに。週刊新潮、東京新聞、プレジデントオンライン、kufuraなどで主にテレビコラムを連載・寄稿。NHKの「ドキュメント72時間」の番組紹介イラストコラム「読む72時間」(旧TwitterのX)や、「聴く72時間」(Spotify)を担当。著書に『くさらないイケメン図鑑』、『産まないことは「逃げ」ですか?』『親の介護をしないとダメですか?』、『ふがいないきょうだいに困ってる』など。テレビは1台、ハードディスク2台(全録)、BSも含めて毎クールのドラマを偏執的に視聴している。



