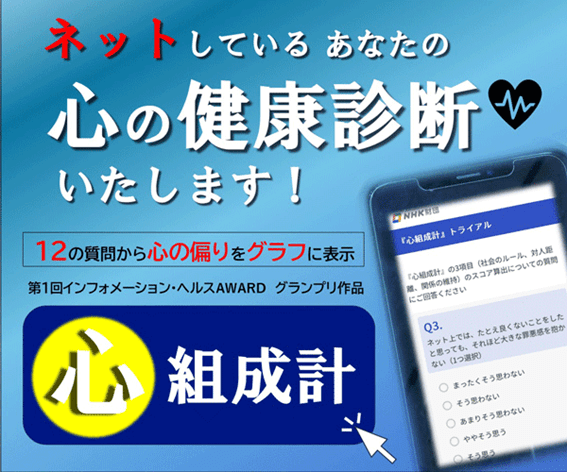関東大震災から100年の今年、6月から8月まで台風・大雨・猛暑などの異常気象が頻発し、連日放送は災害報道モードとなった。
こうした機動的な報道体制は、放送局の長年の努力の結果である。ただしラジオ時代やテレビの初期は、残念ながら課題が山積みしていた。
しかも被災者やその家族・知人にとっては、安否情報へのニーズも高い。ところが放送は安否情報では十分機能せず、通信がITで飛躍的に進化する中、近年になって体制がようやく整ってきた。
災害報道の100年を振り返る。
ラジオ時代の報道 ~停電の壁~
残念ながらラジオ時代の災害報道はお寒い限りだった。
まず1934年9月の室戸台風。日本上陸時の気圧は911.6ミリバール。当時の世界記録だった。日本各地に大きな被害をもたらし、死者は3036人、全半壊・流出家屋は9万戸を超えた。
そもそも気象台の観測能力が低かった。
併せて気象台と放送局との連絡手段が脆弱で、さらに放送局もラジオを受信する各家庭も停電への対応能力に欠けていた。
実際にはラジオは数時間前の気象状況しか発信できなかった。
しかも停電で大半の家庭には届かなかった。防災の役割は全く果たせなかったのである。
状況は戦中戦後でも変わらない。
戦中では43年の鳥取地震、44年の東南海地震、45年の三河地震で放送は非力だった。また終戦直後の枕崎台風、46年の南海地震、48年の福井地震でも、被害状況を十分に発信できなかった。
一貫して防災・減災の役割は果たせなかったのである。
テレビ黎明期の報道 ~伊勢湾台風で力を発揮~
テレビが開局すると、報道は進化を始める。
それまでの「読む」新聞と「聴く」ラジオから、テレビは「見ながら聴く」ニュースとなった。ただしテレビ報道の体制は十分ではなく、放送時間も少なく、機動力や速報性にも欠けていた。
それでも59年の伊勢湾台風を機に、災害報道は変わり始める。
気象台も台風の進路予想や危険予測の精度を上げていた。NHKは超大型台風の接近に対して、気象庁からの中継を初めて行った。従来の“被害の報道”から“防災のための報道”に重点を置いた最初だった。
それでも伊勢湾台風の被害は甚大となった。
死者・行方不明者が5千人を超え、観測史上最悪となってしまった。では“防災報道”が行われたのに、なぜ被害はかくも大きくなってしまったのか。最大の原因は停電だった。
過去の教訓を活かして放送局は非常用自家発電機を稼働させていた。ところが受信者側は、電池式ポータブルラジオの普及率が低く、大多数の人々が情報を受け取れなかったのである。
それでも伊勢湾台風では、被災後に放送が力を発揮した。
ラジオでは安否情報や、生鮮食料品の入荷などの生活情報が役に立った。テレビも台風の惨状を映像で伝え、全国からの支援につなげた。
災害への対応には様々なフェイズがあることを、伊勢湾台風は明確にしたのである。
ニュース拡大と災害報道 ~機材の進化と放送の限界~
災害報道はテレビニュースの発展と共に進化を遂げていく。
70年代以降、報道番組は質量ともに拡充される。夜帯では74年開始のNHK「ニュースセンター9時」、80年のTBS「報道特集」など報道番組が増えていった。
フィルムからビデオへとカメラが代わり、ロケの機動性と速報性が高まったことが前提にあった。
朝帯も変わった。
79年日テレ「ズームイン!!朝!」、80年NHK「ニュースワイド」などの登場だ。そして85年からテレ朝が平日夜を帯で「ニュースステーション」を始めた。TBSも「NEWS23」、テレ東も「WBS」など、各局が帯ニュースを編成するようになった。ニュース戦争の勃発だった。
災害報道も機材の進化と共に充実する。
例えば85年8月の日航ジャンボ機墜落事故。御巣鷹山で生存者が救出された模様を、フジテレビはヘリコプターで電波をつなぎ、スクープ映像を生中継した。
93年7月の北海道南西沖地震では、奥尻島を津波が襲った。
この後に気象庁は新システムを導入し、テレビ局とオンラインで結ぶようにした。各局も自動的に字幕表示システムを導入し、一刻も早い地震・津波情報を流せるようになった。
そして95年1月の阪神・淡路大震災。
地震の瞬間を映像に残すためのスキップバックレコーダーが開発された。2011年の東日本大震災では、海岸線沿いに多数置かれた天気カメラや行政の監視カメラが、各地を襲う津波の生中継を可能にした。
以上のように技術の進歩で、災害報道は年々進歩した。
それでも被災地の住民や被災者本位かと、放送での災害報道では課題や限界が言われるようになった。
阪神・淡路大震災の課題 ~大災害と安否情報~

課題が問われた最初は、1995年1月の阪神・淡路大震災だった。
放送による安否情報に限界があることが認識されたからである。
同震災の規模はマグニチュード7.3。
震度7の激震が人口150万の神戸市をはじめ、周辺の都市部を直撃した。その結果、犠牲者は6434人、倒壊した建物は25万戸ほどに及んだ。
この時点では、戦後に日本で発生した自然災害として最悪のものとなった。
この時に安否情報のニーズが劇的に高まった。
あまりに大きな被害に際し、全国各地から家族・親戚・知人の消息を問う声が殺到したからだ。NHKはFM放送と教育テレビで対応した。
放送時間はFMで162時間30分、教育テレビで連続136時間に及ぶものだった。
ただしこのシステムには課題が残った。
受け付けた情報は5万件超だったが、放送できたのは3万件あまりに留まった。しかも情報を探す側からすれば、特定個人の情報がいつ出てくるかわからない。
何時間も何日も放送をチェックすることは不可能という問題だった。
安否情報の進化 ~データ放送の活躍~
この問題は2004年の新潟県中越地震で前進した。
マグニチュードは6.8だが、直下型のためにこの時の震度も7を記録した。阪神・淡路に次ぐ2回目だった。
死者は68名、建物の全半壊は約1万7000棟に及んだ。
この時には、大都市から順に地上デジタル放送が始まっていた。
これにより地上波テレビ放送は、高画質・高機能・多チャンネルが可能だった。そこで安否情報では、データ放送が活躍した。
データ放送はカルーセル伝送方式が用いられている。
この技術により、視聴者は放送された情報から必要な部分を自由に選びとることが可能となった。つまり阪神・淡路大震災では、何時間も待ち続けなければならなかったが、今回は視聴者が自ら探しに行けるようになったのである。
データ放送は被災者向けの生活情報でも前進した。
郵便番号別に受け取る情報を分別できたため、広域向け情報以外に、自分の住む地域向けの給水や支援物資情報などを受け取り易くなった。
マスメディアの欠点だった個別ニーズを一定程度掬い上げられるようになったのである。
東日本大震災で変化 ~検索型安否情報の導入~
安否情報がさらに進歩したのは、2011年3月の東日本大震災だった。
マグニチュード9.0、犠牲者は2万2318人。日本における観測史上最大の地震だった。
この時のNHKは、データ放送で初めて検索型の安否情報を導入した。またグーグルのパーソンファインダーとも連携し、避難者名簿を検索できるシステムも導入した。民放も事実上の検索型サービスを始めた。TBSはYouTubeで避難者の映像メッセージを配信する消息情報チャンネルを始めた。日テレもインターネット配信サービスの第2日テレで、フジも自社HP上で続いた。
安否情報の確認は、放送よりネットの方が機能すると確認された瞬間だった。
安否情報以外にNHKは、テレビの同時再送信を緊急時特例として行った。
続いて民放各社も、同様のサービスに踏み出した。実際に放送をPCやモバイルで受けられると、災害で送信施設が止まっても、通信の合理的な伝達システムで補完されやすい。
さらに端末は携帯性に優れバッテリーで稼働するため、格段に利用シーンも増える。例えば山間地や沿岸地域で活動する人々もカバー出来たのである。
以上のように、災害報道の多くの部分は、通信の特性を活用して利便性が高まった。昭和の三大台風(室戸・枕崎・伊勢湾)の時と比べれば、被災者にとってメディアは格段に力を発揮するようになったのである。
特に安否情報は、大災害の際には情報が膨大になるゆえ、放送で担うには限界があった。東日本大震災で証明されたように、多くの情報からオンデマンドかつピンポイントに検索できるシステムが必須だ。
この意味では関東大震災後に、制度的に放送は通信から切り分けられたが、技術の飛躍的な進歩を受け両者は融合、あるいは連携することに合理性があると見えて来た。
シリーズ3回目では、放送と通信が今後どんな関係となり、メディア全体が災害報道でどう機能するのがベストなのかを考える。
【防災プロジェクト 関東大震災から100年】関連番組
NHKスペシャル「映像記録 関東大震災 帝都壊滅の三日間」(前・後編)
9月2日(土)午後10時~/9月3日(日)午後9時~ NHK総合(2夜連続放送)
関東大震災の発生からの3日間を当時の記録フィルムに残された映像を高精細・カラー化して追体験。甚大な被害を招いた帝都壊滅の3日間の全貌に迫る。
前編(9月2日初回放送)の公式ページはこちら
後編(9月3日初回放送)の公式ページはこちら
愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。